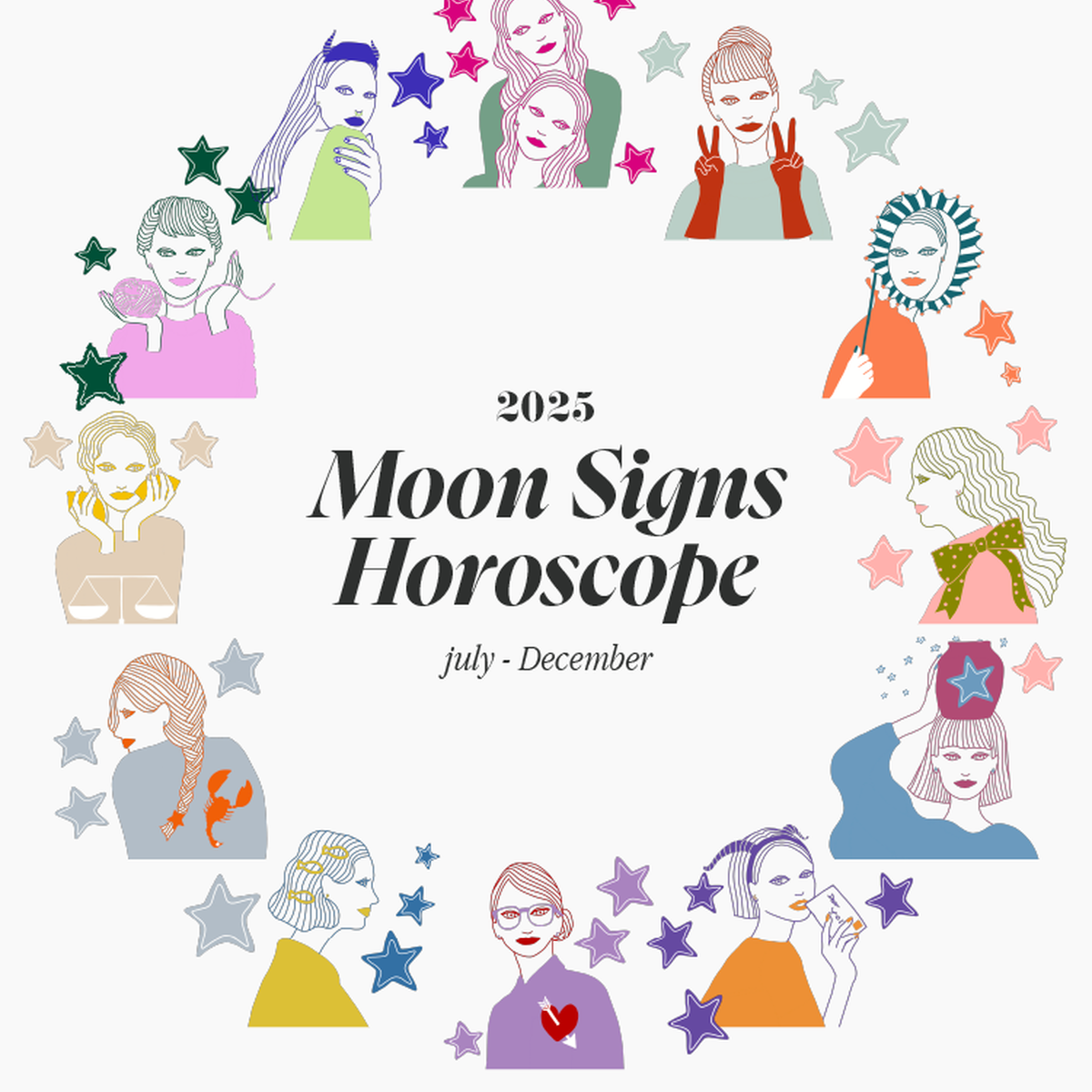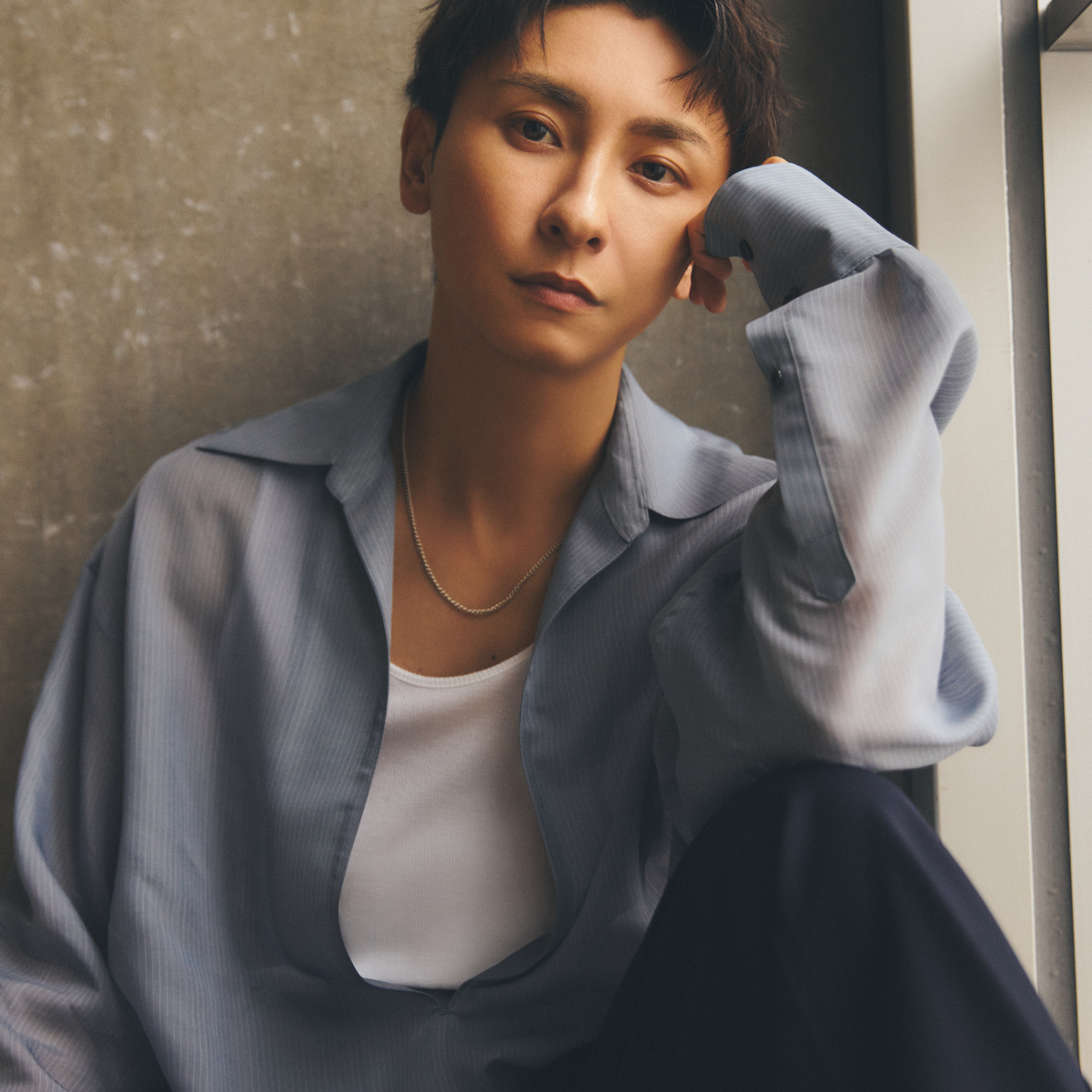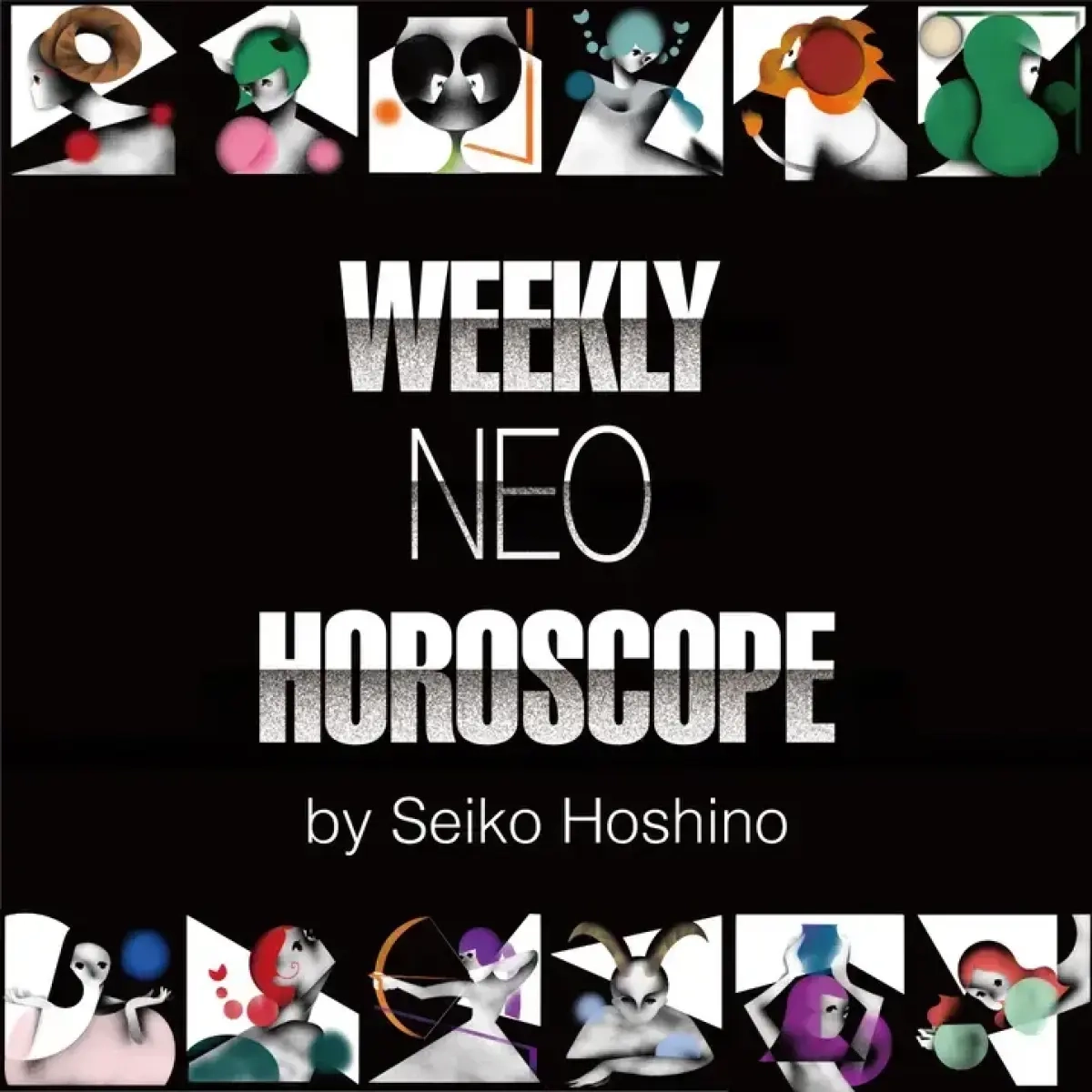メンタルヘルスの問題やジェンダーによる固定観念などに向き合うフランス・パリ在住のアーティスト前田英里さん。私たちが抱える生きづらさの根源に気づかせ、心を軽くしてくれる作品を数多く生み出しています。インタビュー後編では、結婚を機にパリへ移住した彼女が、「こうあるべき」という呪縛からの脱却にどう向き合ったのかを伺いました。
アーティスト
1989年生まれ。フランス・パリ在住。大学卒業後、グラフィックデザイナーとしてキャリアを積んだ後、2017年にセラミックアーティストへと転身。これまでにストックホルム、ミラノ、パリ、ロンドンなどで個展を開催。2024年11月には、東京では自身初となる作品展「不適切な展示会」をラフォーレ原宿にて開催し、大きな話題を呼んだ。
「こうあるべき」を「Lipstick Monster(リップスティックモンスター)」が食べ尽くす

——最新作が、「Lipstick Monster(リップスティックモンスター)」とのことですが、この作品にはどのような想いが込められているのでしょうか。
前田英里さん(以下、前田さん):美しいを作り出す口紅の先がモンスターの口になっている「Lipstick Monster」は、画一的な美の価値基準や、「女性はこうあるべき」「母親はこうあるべき」といった、社会が押しつけてくる価値観への反抗心を表現しました。リップスティックモンスターは、そうした古い固定観念を食べ尽くして自由にしてくれる存在なんです。
――今、お話にも出てきた「母親はこうあるべき」という固定観念に、前田さん自身も悩まされたことがあるのでしょうか。フランスで出産・子育てをされていますよね。
前田さん:はい、ありますね。日本で生まれ育った私は、母親になったら家族に尽くさなきゃいけないと思い込んでいたので、出産して1カ月後、アイデンティティクライシスに陥ったんです。このままでは自分がダメになってしまうと思い、パートナーに「仕事(陶芸)を再開したい。アトリエで土を触りたい」と伝えたら、すぐに「行っておいで! 英里が幸せになることをして。ここまでお疲れさま」と、仕事復帰を後押してくれて。それに義親や友人たちも「英里はそうすることにしたんだね!」と私の決断をリスペクトしてくれて、おかげで自分を取り戻すことができました。
フランスでは、母親という役割ではなく、一人の人間としてその人自身を見て、尊重してくれる文化があります。例えば、私は家事が得意じゃないので夫が料理を担当してくれてるのですが、それも「普通のこと」として受け入れられている。ほかにも今回、私は個展を開催するにあたり、夫と話し合い、日本に一人で帰国したんですね。日本にいたときに抱いていた私の母親像だと「母親なのに1カ月近くも家を空けるなんて…」と思われてしまうかもしれないことですが、フランスでは「それが家族にとってベストな選択なら、それでいいんじゃない?」と特別視されることなく受け止められるんです。
日本は「母親」という肩書きの責任がとても重く、それを基に自分を確立していく人が多いように感じます。それも素敵なことですが、私が母親になって感じたのは「子どもは自分のものではなく、一人の独立した存在」だということ。だからこそ、「前田英里」という一人の個としてしっかり存在したいんです。妻であり母である前に、自分自身を大切にしたいから、「Lipstick Monster」とともに「こうあるべき」に縛らずに自分らしく生きていきたいですね。

「Lipstick Monster(リップスティックモンスター)」
『カワイイ』って誰が決めるの?
リップスティックモンスターは「だまれぇー!」と叫び噛みつく。
美の基準やジェンダーのルールを飲み込む牙むき出しのリップスティック。
それは“こうあるべき”への反抗の象徴。
シュルレアリズムに影響を受けた私の作品は、
美の押しつけにNOを突きつけるメッセージを描く。
Eri Maeda
マインドフルな世界を目指して、私はベイビーフェミニスト!

——今回、久しぶりに帰国して日本で過ごされていかがですか。
前田さん:正直に言うと……今回の帰国で日本と仲直りできると思っていたんですが、そう簡単にはいきませんでした。理由はいくつかあるのですが、ひとつは、家族を持つ知人たちとの会話です。ある子育て中の数名の知人が「飲み会の写真をインスタのストーリーにアップすると罪悪感を感じるし、他人の目が気になる」と話してくれたんです。そのときに、先ほどお話しした「母親はこうあるべき」という固定観念が根強く残っていること、さらにはそれを生み出している男性中心の社会構造が、いまだに日本に深く根付いているのだと感じました。
もう一つは、「注意書き」の多さ! 例えば、「柱に注意してください」とか、「香りがきつくなるので、柔軟剤の使用量には気をつけましょう」など。そこまで書かないとダメ?と思うような注意書きがあちこちにあることに気づいて。失敗を防ぎ、考えさせないためのルールが日常にあふれていて、まるでルールがないと生きられないようになっていると感じてしまったんです。
もちろん、こうしたルールのおかげで、日本は電車がオンタイムに来るし、どこに行ってもキレイで安全な社会になっている。それは本当に素晴らしいこと。だけど、こうした細かなルールの多さが私たちを窮屈にしている側面もあるんじゃないかなと。また、ルールを守ることに慣れすぎてしまい、本来アップデートすべき古いルールまでいまだに守られ続けているのではないか……そんなふうに思ったんです。
——夫婦別姓をはじめ、結婚に関する制度がなかなか進まないことにも通じるお話ですね。
前田さん:そうなんです、もう「なんで?」という疑問が次から次へと湧いてきてしまって。最近少し落ち着いていた社会への反抗期がまた到来してしまいました(笑)。
実は昔、「フェミニスト」と聞くと「うるさいおばさん」という偏見を持っていました。でも今では「そりゃうるさくなるよね」と完全に理解できます。社会の矛盾に気づけば気づくほど、声を上げたくなるものだから。私自身は、まだ「ベイビーフェミニスト」だと思っていて、フェミニストに目覚めたばかり。3歳児があらゆることに、「なんで?」と問いかけているのと一緒の状態です。
でも、正直に言うと、私は「ベイビーフェミニスト」ではある一方で、フェミニストという言葉にまだ苦手意識が残っています。というのも、"フェミ"という言葉自体が女性的な印象を与えてしまい、男性がフェミニズムムーブメントに加わることをためらわせている要因になっていると感じるから。実際、女性が女性らしさから解放されるためには、男性が男性らしさから解放される必要がある。その意味で、男性にもフェミニストの考え方が必要不可欠なのに、この言葉が持つニュアンスが壁になっているのではないかなと。
だから、個人的に「マインドフル」という考え方を軸にするのがいいではと考えています。そうすれば、性別に関係なく、すべての人をインクルードできるから。例えば、「マインドフルな会社」を目指せば、子育てをする男性が育休を取得したり、時短勤務をしたりすることも自然に受け入れられるようになるはず。
——確かに、男性も「こうあるべき」から解放されることが、社会を前進させるうえで必要不可欠ですよね。前田さんは、そういった「こうあるべき」に縛られている人に対峙したときにどういう対話をされるのですか。
前田さん:別にその人の思考に正解も不正解もないですが、「なぜそう考えるの?」と質問攻めにします。トキシックマスキュリニティ(有害な男らしさ)は、ひとりでに育つものではないですよね。どんな親や家庭環境で、どういうことを言われて育ったのか……そういったすごく深くて見えにくいところに、「男はこうあるべき」の種が埋め込まれていて、その人をがんじがらめにしているだけだと思います。だから私は、そういう人と「戦う」のではなく、その人の根っこの部分を理解するように心がけたいですね。どんな人に対してもマインドフルで、受容的な生き方を模索していきたいと思っています。
そういえば、「Side Effect(サイドエフェクト)」という作品では「女性・男性らしさ」に縛られることでつらくなり、お酒やタバコに依存してしまう現象を表現しています。この作品が、自分のなかに埋め込まれた「こうあるべき」に気づくきっかけになったらうれしいですね。

「Side Effect(サイドエフェクト)」
「感情的に閉ざされている(Emotionally unavailable)」って、
自分や他人の感情に向き合うのがちょっと面倒で、
ついお酒やタバコ、買い物、SNSスクローリングで気を紛らわせたくなっちゃうこと。
これ、「コーピングメカニズム」って呼ばれる一時的な対処法で、気持ちが楽にはなるけど、
根本的な解決にはならない。むしろ、繰り返すうちに、知らず知らず依存しちゃうことも…。
Side Effectでは、そんな「コーピングメカニズム」が
どんな影響を心に与えるのかを描いています。
Eri Maeda
——最後に、前田さんは今後どのような活動をしていきたいと考えていますか。
前田さん:インターナショナルアーティストとして、パリを拠点に活動しつつ、1〜2年に1回は帰国して個展を開催したいです。というのも、今回一時帰国して開催した個展で、「Emotional Baggage(エモーショナル・バゲージ)」という作品を展示したんです。この作品は、紙に書き出した心の内に抱えている感情や不満をポストすることできるバッグで、SNSのリアル版のようなものです。今回、そこに寄せられたお悩みに目を通したら、ここまでお話ししてきたようなトピックについて多くの人が悩んでいることを実感しました。そういった人たちがもっとラクに、自分らしく生きていけるように、ヨーロッパで暮らして感じたこと、見つけた生き方を選択肢のひとつとして、アートを通して提案していきたいです。

「Emotional Baggage(エモーショナル・バゲージ)」
「エモーショナル・バゲージ」は、感情の重荷を手放すことをテーマにしたインタラクティブな作品です。
自分の気持ちや思いを紙に書いて、バッグの形をした彫刻の中に入れることで、
心の中に抱えている重荷を解放し、気持ちが少し軽くなるような体験ができます。
過去の出来事やトラウマと向き合いながら、自分自身を見つめ直すきっかけをつくる作品です。
Eri Maeda
撮影(人物)/Nobuko Baba(SIGNO) 取材・文・企画・構成/海渡理恵