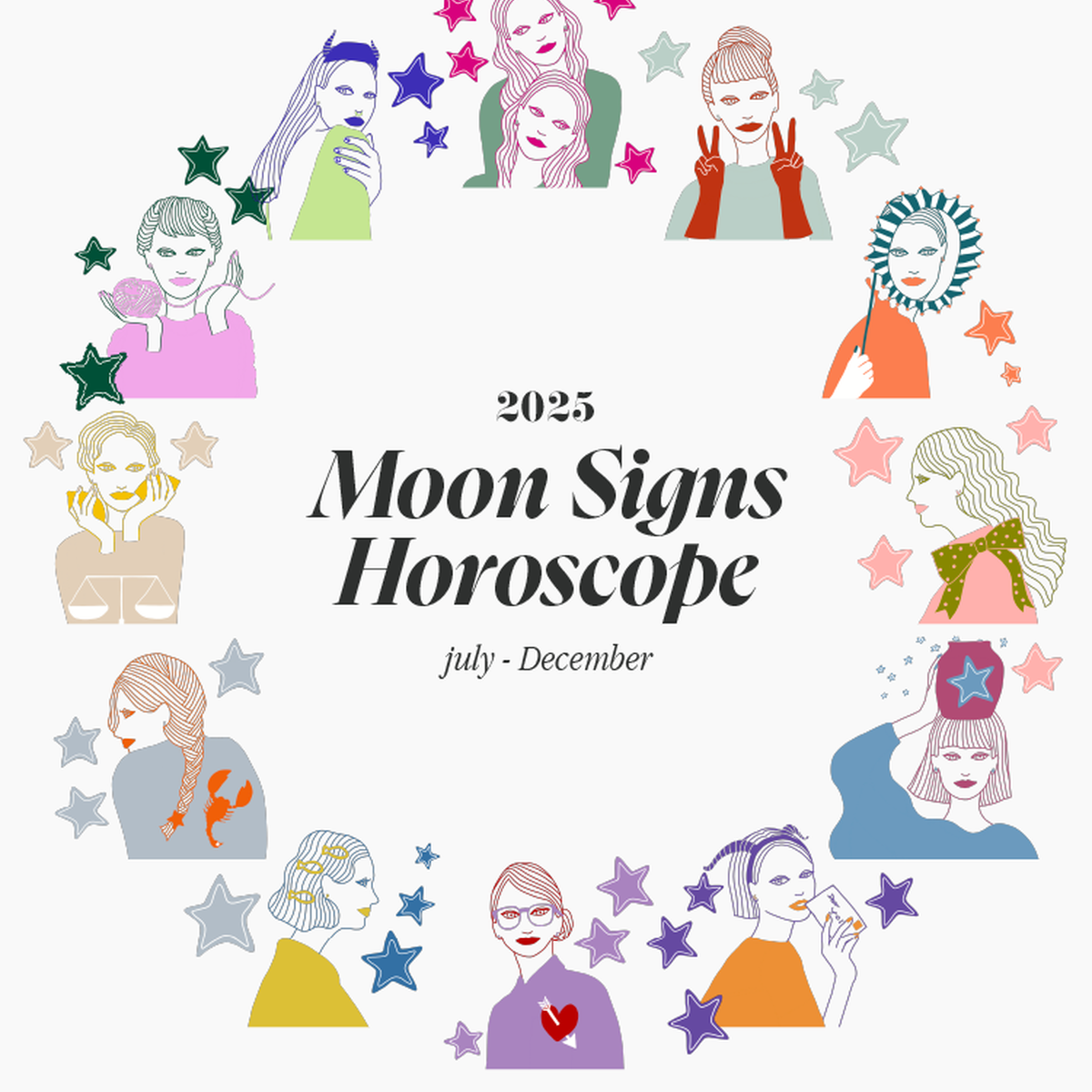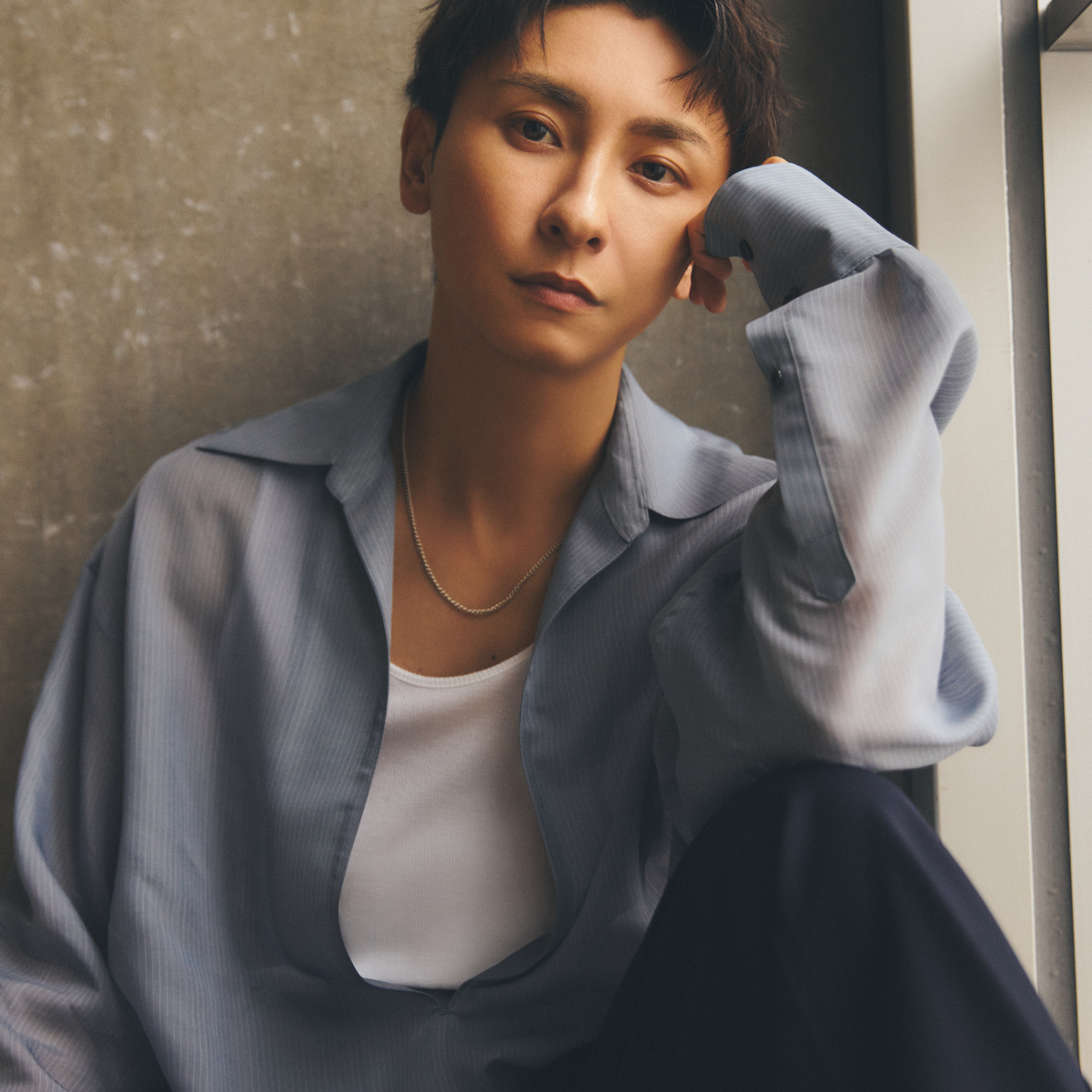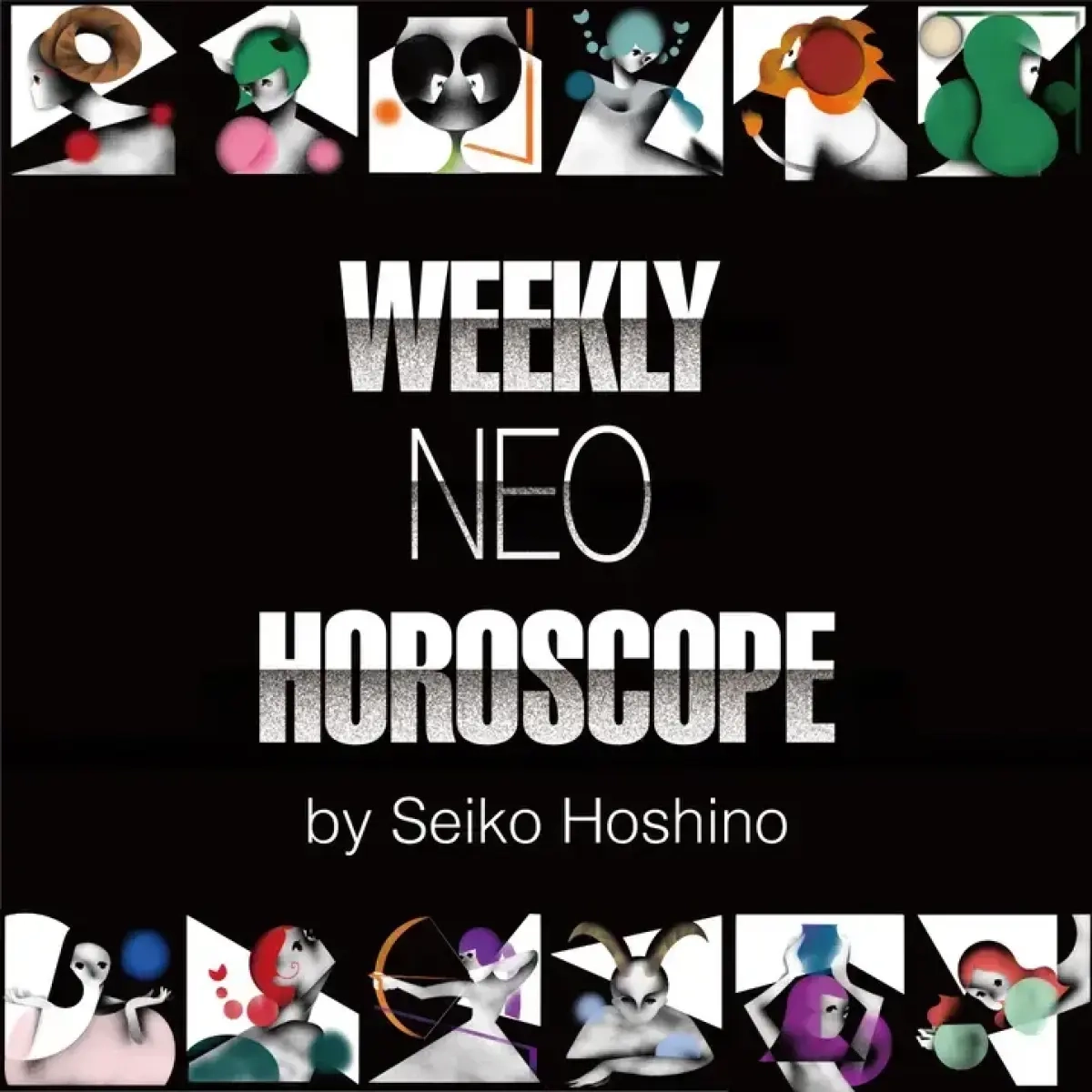自身もミックスレイシャルというバックグラウンドを持ち、美術大学の大学院でマイノリティの方々のリサーチを行っている、yoiクリエイターズのくどうあやさん。本記事では、くどうさんが出会ったマイノリティコミュニティに属する方へお話を聞き、どのような思いでそのコミュニティに属し、社会と関わっているのかを深掘りします。
【yoiクリエイターズとは?】
yoiの読者としての目線を生かし、語学やアート、文章表現などのクリエイティブスキルを発揮して、情報を発信していくクリエイターのこと。ビューティーやウェルネス、カルチャーや社会派の記事など、それぞれの得意分野でyoi読者におすすめのコンテンツを毎月配信します。メンバーは24年10月現在くどうあやさん、石坂友里さん。
今回インタビューをさせていただいたのは、自身もレズビアンであり、クィア(既存の性カテゴリーに自身を当てはめない・当てはまらない人)のコミュニティ「集まるクィアの会」の主催をしている燈里さんです。
台湾で5年間暮らしながら、大学院に通い、翻訳者として活躍。日本に帰国してからは翻訳の仕事をしながら、友人のタンさんと二人で、月に一度「集まるクィアの会」を主催しています。
今回は燈里さんにマイノリティコミュニティを作ることへの思い、自分自身を大切にするためにしていることなどについて伺いました。

ライター・翻訳者
1992年茨城県出身、在住。社内技術翻訳者、執筆者。女性性やクィアを取り巻く歴史、政治、体、呪術を探るエッセイを雑誌やウェブに寄稿。「集まるクィアの会」のコミュニティ・オーガナイザー。
「集まるクィアの会」とは?
クィア当事者や、クィアにまつわる問題に関心を持つ参加者が集まってお喋りをしたり、クィアを取り巻く社会問題について一緒に考えて行動をする会。「孤独に踊るクィアの集い」「お花見・青空本交換会」「映画『これがピンクウォッシュ!シアトルの闘い』の上映会」「スタンディングデモとピクニック」など、毎回場所をテーマを変えて月1回開催している。イベントのお知らせは、燈里さんのInstagramアカウントにて。
クィアのみんなが、遊びも政治的活動もできる居場所を作りたかった
——「集まるクィアの会」には、どのような方が集まっているのでしょうか? そして、どんな活動をしていますか?
燈里さん 参加してくださる人にはクィアの人はもちろん、クィアコミュニティやクィアを取り巻く社会問題に関心がある人もいます。月に1回の開催で、フリマやお花見のような遊びの会と、社会や歴史、カルチャーについて語り合う勉強の会を交互に開催しています。
——「集まるクィアの会」はどのようなきっかけで始めたのですか?
燈里さん 単純に楽しいことが好きなんです。遊ぶことも友達も好きだし。台湾で生活していたときは、よくクラブで集まっているようなクィアコミュニティに出入りしていました。
ただ、台湾から日本に帰ってきたら、自分の居場所になるようなクィアのイベントがなかったんです。台湾だと特に音楽パーティが多いんですけど、日本は音楽パーティとなると本当になくて。「それなら自分で作るか」と思ったのが単純な動機です。
——始めた当初はどのようなことを目指すコミュニティだったのでしょうか?
燈里さん 当初は社会変革を目指していました。今も、その目的は変わっていないです。社会を変えることは個人だけではできないから、そのためのコミュニティを作ろうと思ったんです。なので、遊びも政治的な活動も、どっちもやれるようなコミュニティにしたいと思っています。
私が初めて入ったクィアコミュニティはアクティビズムをしながらも、パーティのような楽しい催しもしているところで、遊びと政治がわかりやすく区切られていなかったんです。なので、自分がコミュニティを作るときにも、当たり前のように「そういうものなんだ」と思っていました。
ただ、日本に帰国したばかりの私が急にパーティを企画しても、知人がいなくて誰も来てくれません。まずは人が集まるコミュニティを作るために、読書会やワークショップ、映画を見て話し合う会などを定期的に開催しています。コミュニティを作ってからパーティを開催すれば、盛り上がるだろうし面白いと思ったんです。
——燈里さんご自身が初めてクィアコミュニティと関わったときのことを覚えていらっしゃいますか?
燈里さん 最初はクィアコミュニティだと知らなかったんです。友達にクラブに誘われて、私も音楽が好きだから行ってみたらアングラのテクノクラブで。実は、そこはクィアコミュニティが集まるクラブだったんです。
初めの数カ月は何も知らなくて、普通に音楽を聞いたり踊りに行っていました。そのうち友達もできたんですけど、なんだかゲイの人が多いなと思って。その人たちと仲良くなったら、彼らがまた別のパーティに連れて行ってくれて。そっちはもっと、ハウスミュージックが流れ、ドラァグショーやヴォーギング(アフリカ系、ラテン系アメリカ人のLGBTコミュニティで発展したダンスカルチャー)をする人が集まっていたり、代表的な“クィアの音楽カルチャー”がある場所でした。最初はそういったクィアのカルチャーを知らなかったので気がつかなかったのですが、知識を得て、クィアのコミュニティだと徐々に知っていきました。
台湾と日本で違う、クィアコミュニティのカルチャー
——台湾に住んでいたときからクィアコミュニティに関わっていたそうですが、日本と台北で大きく違うと感じる部分はありますか?
燈里さん 台湾では、常に誰かがイベントをやってくれていたので、クィアによるコミュニティやアクティビズムがいっぱいありました。私はそれに参加するだけでよかったし、コミュニティ同士でサポートし合っていて、 何か問題が起こってもお互いに支援し合えたりと、 色んなことがうまく回っていました。
日本ではイベントがとにかく少ない。クィアの友達がいないわけではないんですけど、コミュニティにはなっていかなかったり。 だから、自分でやらないと始まらない。そうするともう、私自身がアクティビズムを頑張らないといけないですよね。個人的な変化としては、時間とかに余裕がなくなって、台湾にいたときと比べて、遊んだり趣味のための時間がすごく減ったと思います。
——日本人の性格だと思うんですけど、元々少しシャイな人たちが急に積極的になることは難しいですよね。日本人に合った形のクィアイベントは、どう実現できるんだろうかと思っていました。
燈里さん パーティで踊ったりするのが得意じゃないタイプの方も多いので、パーティではクィア書籍を扱う本屋さんに出店していただいてゆっくり過ごせる場所を作ったり、話を聞くのが得意な人が多いので、トークの時間を設けたり、みんなで楽しめるゲームを入れたり…イベントのやり方で、バランスを取るようにはしています。
パリピの人だけが来るパーティだと人が限られるし、 そういう人たちは別のパーティにいくらでも行けるので。コミュニティがベースにあるパーティにしたいという思いがあるから、私のように、人と話すのが苦手な人でも、ちょっと来て楽しめるスペースがあるようにしたいなと。だから、「孤独に踊るクィアの集い」というタイトルでパーティをやってみたりしています。
私が最初にクィアコミュニティに入ったパーティで、初めて本物のドラァグクイーンを見たときに、「私もここに入れるんだ」って思ったんです。音楽もかっこいいし、他のクィアの子たちもみんな一人一人が好きな格好して恋愛を楽しんでいて。そんなクィアのカルチャーがとにかく楽しくて、「みんながいてくれるから、ここが自分の居場所なんだ」と思う体験でした。日本版では、バランスをとりながらも、私が体験したような喜びが生まれるパーティにしたいなと思ってます。
実験的に毎月イベントの内容を変えてみたりもしていて、真面目な勉強会やフリマなど、テーマによって集まる人の雰囲気も全然違っています。合わなかったら合わなかったでいいし、好きなテーマのときに参加してくれればいいと思っています。とはいえ、いまだにどうすればいいのかあまりよくわかっていない部分も多いです。
日本版クィアコミュニティで、自己表現ができる個人を増やしたい

——みんなで共通して盛り上がれる鉄板ネタみたいなものはあるんですか?
燈里さん 台湾にいたときは星座でしたね。星座といえばゲイカルチャーなんです。おそらく西洋の方もそうです。それは本当に助かっていました。
実はクィアで集まるとみんなバラバラで、あまり共通点ってないんです。例えば、 レズビアンとトランスジェンダーの男性とか、ノンバイナリーの人とゲイとか。恋愛話でも、共通項がなかったり、聞いてはいけない雰囲気もあります。いきなり「セクシュアリティーなんですか?」なんて、失礼だから聞かないと思うんですよ。
でも、星座はみんな好きで、よく知ってるんです。初対面では名前の次に星座を聞かれて、それでわっと盛り上がって、星座の話だけで3時間も4時間も話しているんです。星座って、みんな12個のうちのひとつを持ってるじゃないですか。それで、「〇〇座ってこういう感じだよね」って話すんです。逆に「私はそういうタイプじゃなくて」というのも、それはそれで自己紹介になったりして。
——コミュニティとしてこれから実現したい形はありますか?
燈里さん 性的マジョリティの人たちと会って違和感を感じて、同じクィアの人たちがいるところだけでしか自分を表現できないとか、居場所がない、話せないと感じている人たちがすごく多い中で、「集まるクィアの会」を通してちょっとずつアウトできる、そういう個人が生まれるような集まりになっていけたらいいなと思ってます。
それは必ずしもカミングアウトするって意味ではなく、ただなんか一言言えるとか、 ちょっと自分を表現できるとか、自分のまわりで、それぞれの居場所を自分で作っていけるような個人が増えたらと思っています。
そのためには、クィアであることは被害者で可哀想な人たちではなくて、祝福されるべきこと、プライドと喜びがあることだと実感してもらいたいです。その意味では、特に音楽パーティはクィアカルチャーを広げてみんなで作っていくための大切な場所になると思っています。
何かカルチャーがあるって素晴らしいことだと思うから、それを感じてクィアってかっこいいなとか、楽しいなと感じられる場所になるといいかなと思います。それはやっぱり、リアルな場でしかできないことだと思うんです。
当事者でなくても、イベントに来ることで気づけることがある
——マイノリティコミュニティは、「当事者でないと入ってはいけない」と壁を感じる人もいるかと思います。当事者でない人が関わることについて、燈里さんが考えていることがあれば教えてください。
燈里さん 楽しいイベントをやっていると色々な人が来てくれます。なかには、後になって自分はもしかしたらクィアなのかもしれないって思う人たちもいるでしょうし、今はどっちかわからないという人もいたりとか。だから、参加者は当事者だけには限定していなくて、誰でも来てほしいと思ってます。
ただ、もちろん主役はクィアの人になるので、それを尊重してくれる人限定にはなっています。差別ももちろん禁止です。クィアってどういう人たちなんだろうって知りたい人もたくさんいるでしょうし、そういった人も歓迎しています。
——世間で“普通”とされている性的指向と自分が違う、と違和感を感じていても、自分が性的マイノリティ側なのか自信を持って言えない人って、実はすごく多いと思うんです。
燈里さん もしそう感じていたとしたら、その違和感に向き合うことは、すごく大切なことだと思っています。「異性愛者ではあるけど、自分の性別は100パーセント女と言えるんだろうか」とか、「少し普通とは違うファンタジーのような恋愛観を持ってる」とか、人にはそういうグレーな部分が結構あると思うんですよね。
私たちのイベントは、自分を内省したり、セクシャリティを見つめ直す機会になったらいいと思ってます。そこからマイノリティの人たちの見え方とか関わり方も確実に変わってくるはずです。
常にマジョリティでいるのって絶対しんどいと思うんです。マジョリティって時代とか権力者によっても結構変わりますから、常にまわりに合わせてマジョリティにならないといけないことは、本当はしんどいことだと思います。
もしも、相手の発言に「モヤッ」としたら?
——コミュニティの外でも人と関わっていると、誰かの発言などに対して差別意識を感じたり不快感を感じることもあると思うのですが、燈里さんはそういうときでも、自分の意思をはっきり伝えるようなタイプですか?
燈里さん 私はクィアコミュニティの中でも外でもあまり変わらないので、同じような反応をすると思います。はっきり糾弾したり怒ったりはしないですけど、「それはどうかな」みたいな感じです。差別的な発言に対して、賛同しないとか、笑わないとか、面白くないといった反応を出しておくと、向こうもちょっと引っかかって同じことを言わなくなったりしますから。相手が「なんでそう思わないのか」って聞いてくれば、そこから話が始まるので、その際のコミュニケーションは大切にしています。
もし誰かが私の発言に引っかかったとしたら、同じようにしてほしいと思っています。クィア関連でも、私が色々知ってるつもりだったとしても、やっぱり自分と違うセクシュアリティの人のことはわからなかったりすることもあります。
マイノリティコミュニティの人は人数的にもマイノリティなので、基本はマジョリティの人たちと一緒にやっていかないといけないわけじゃないですか。関係性を築く努力をお
——クィアコミュニティの外の人と関わるときも、変わらないのですね。
燈里さん 自分の意識としてはあんまり変わってないです。意外と仕事でも学校でもクィア会でも、キャラクターは変わってなくて。ただ「集まるクィアの会」では一応前に立たないといけないので、少し声を張ったり、まとめ役をやるけれども、基本的なキャラは同じです。仕事でも、普段と変わらない感じでやらせてほしいというタイプですね。
自分の心地よいバランスで続けています

——SNSで燈里さんのことを拝見していると、非常にアクティブに活動されているという印象を持ちつつも、自身のネガティブな部分を非常に大切にされているように感じます。自身の飾らない姿を公開していることに魅力を感じているのですが、自分を見せるということについて考えていることはありますか?
燈里さん クィア会とかアクティビズムの活動は、「社会をよくしたい」という目的があるので、多少無理をしてでも前に出ていくように頑張ってますね。
ただ、本来はそういう性格じゃないので…本当は陰キャで絶対人前に出たくないんです。だから他の時間は一人で静かにしてバランスを取っています。仕事も完全に一人で成立して、誰とも喋らずに家で全部できちゃう内容なんです。週末はデモとかパーティとかのイベントに行くので、それでうまくバランスを取れているかなと思います。
——自分のために続けている習慣はありますか?
燈里さん やっぱり書くことですかね。手帳に全部書き出します。SNSを見すぎたりとか人の目線が気になりすぎると自分の本当の声がわからなくなるので、いったん考えてることを全部書き出して、そこに預けて忘れちゃうんです。一人になって書いていると、自分に戻れるような感覚があります。
どこにいても「規律正しい善良な人でなくちゃいけない」というプレッシャーが強いので、その思いを日記に書いて、自分で「こういう側面もあるな」って自覚するのはいいことだと思っています。書くことが思いつかなくても、自分が何かを書きたいと思ってる状態なのだと気がつくことで、自分自身を理解することもできます。
——ノートにすごくたくさんのメモを書いている様子を、SNSに載せているのが印象的です。
燈里さん この習慣は、字を書き始めたときから続けているんです。今のスタイルになってからは、13年ぐらいかな。家から都心までの行き帰りで1時間かかるので、その間に結構な量の本を読みながら、書き込んでいます。
——燈里さんは、自分自身のために使う時間を大切にしているように見えます。自分の時間と仕事やコミュニティ活動に使う時間をどのように管理していますか?
燈里さん 私は10時間は寝ないといけなくて、長いと18時間寝ることもあるんです。そうすると、一般の人より明らかに使える時間が短いので、基本的にはあんまり時間を無駄にしたくないと思っています。私にとって仕事は興味もやりがいもあるけれど、生活のためにやってる部分が多いんです。なので静かに一人でリモートでできて、体力をそんなに使わないことが条件になっています。翻訳の仕事は単調な作業で、瞑想をしているような感覚です。仕事をすることで落ち着いて、アクティビズムは体力を使って頑張りたいです。
イラスト・構成・取材・文/くどうあや