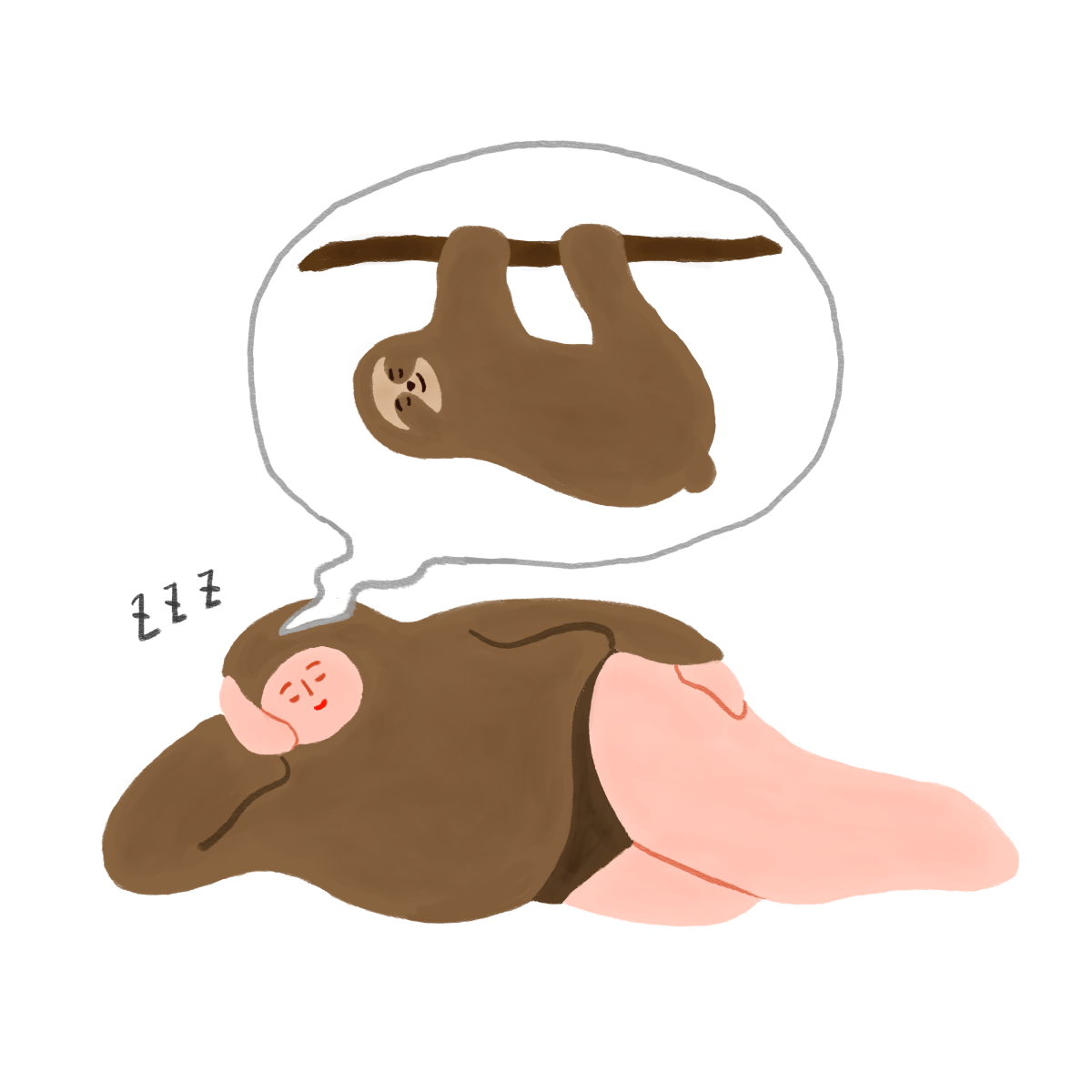つわりや、日々重たくなる体を支える妊娠期間を経て出産。ようやく体がラクに.....なると思いきや、実際は「出産後の体がこんなにボロボロになるなんて聞いてなかった!」と思うことがたくさん。出産って思いもよらないことの連続。出産経験者によるリアル座談会から産後うつ、ケア施設体験まで、3月5日の産後ケアの日にちなみに出産や産後に関する記事をまとめてご紹介します。
- 産む前に知りたかった! 30代の「出産後の体」はこうなるリアル座談会
- 無痛分娩でも、体へのダメージは不可避
- 出産後の体のしんどさと会陰問題
- 母乳問題・むくみ問題
- 出産後の体の変化は? セックスは? 子どもとの向き合い方は? シオリーヌの出産&育児体験記
- 授乳後のおっぱいは、梅干しみたいにシワが寄る!
- 寝る間もない子育て中は、「セックスなんて無理」が本音かも
- 生き方もジェンダーも、いずれこの子が決めること
- 子どもがいても、自分の人生を充実させる意味
- うっかりミスに集中力の低下…これってもしかして「マミーブレイン」? 出産後の変化に落ち込むKさんのストーリー
- 産後10カ月で仕事復帰するもミスの連続
- さまざまなダメージの蓄積が引き金に
- 心と体の違和感に気づいたら迷わず相談
- お互いに歩み寄りながら選択肢を増やす
- 自分が元気になるための時間をつくる
- ガルガル期、上の子可愛くない症候群、産後うつ病…経験者が語るメンタル変調のリアル 「Stories of A to Z」Story14
- 「上の子可愛くない症候群」かも…と自己嫌悪に陥ったLさん
- 「上の子可愛くない症候群」かも…と自己嫌悪に陥ったLさん
- 一人育児と二人育児はまったく別物。ゼロからのスタートだと考えて!
- 二人同時に愛することはできる。ただ、手が足りないだけ
- 産後うつ病の治療をしたいけれど、ワンオペ育児で治療をためらうMさん
- 主治医、パートナー、家族…みんなでサポート体制を整える
- 子どもは社会で育てるもの。一人で抱え込まないで
- 身近な人の言動が気になってイライラが止まらなかったNさん
- イライラのパターンを分析してみる
- 自分なりの切り替えTIPSを見つけておく
- 【産後ケア施設体験】働く母が活用するメリットとは? 費用や一日の過ごし方etc.出産後のライターがレポート!
- 注目度上昇中! 産後ケア施設とは?
- かかる費用や選ぶ基準のリアル
- いざ宿泊! 産後ケア施設での過ごし方をレビュー
- 【夕方~夜】お部屋にチェックイン
- 【朝】家事からの解放を実感!
- 【昼】友人の面会や美容室へ
- 【夜】家族とともにゆっくり就寝
- 【チェックアウト】心温まる心遣いも
- 働く女性が、産後ケア施設を利用するメリットは?
- Mamma Levata(ママ レヴァータ)
- 今話題の「産後ドゥーラ」って何? 成り立ちからサポート内容、料金目安、家事代行との違いまで専門家が解説!
- 「産後ドゥーラ」とは? どんなサポートをしてくれる?
- ●不安定になりやすい産前・産後の母親をサポート。ベビーシッターや家事代行との違いは?
- ●料金体制は? 何歳まで利用できる?
- 講義、実習、テスト、面談。養成講座で産後ドゥーラの高い質を保証
- ●資格取得の方法
- ●資格取得までの期間は? 費用は?
- 「産後ドゥーラ」として働く桑原恵美さんの仕事内容
- 親も子どもも、個性があるから。教科書どおりにできなくて当たり前
- “産後ダイエット”以外の健康管理を考えたい! 体重管理をしない新しいパーソナルトレーニングの形
- これまでは「ダイエット」でしか自分の体に向き合ってこなかった
- 体重測定も、無理なトレーニングもない。新しいパーソナル健康管理の形
- 自分のために、「アンチエイジング」ではなく「ウェルエイジング」を目指す
- 【優木まおみのフェムケアエクササイズ】PMSや出産後の悩みに。今日からできる骨盤底筋の鍛え方
- 正しい姿勢から、骨盤底筋やインナーマッスルを鍛えることが大切
- 膣のゆるみにも効く! 骨盤底筋を自然に鍛える「正しい立ち方」
- 骨盤底筋が鍛えられる正しい立ち姿勢とは?
- 骨盤底筋が使えていないNG姿勢
- 骨盤まわりを整え、インナーマッスルを鍛えるエクササイズ「ダイナソー」
- ①股関節とインナーマッスルのストレッチ
- ②腸腰筋の強化につながるエクササイズ
産む前に知りたかった! 30代の「出産後の体」はこうなるリアル座談会

yoi副編集長
37歳 こども6歳(2018年・無痛分娩)
昨春からyoi編集部副編集長に。吸水ショーツやPMSサプリなど、フェムテック関連のアイテムは昔から積極的に試してみるタイプで、今いちばん気になっているのは「月経ディスク」。息子と過ごす時間が何よりも幸せ。

ライター
39歳 こども7歳(2017年・帝王切開)/5歳(2019年・帝王切開)
yoiライター。産後をきっかけに、ホルモンバランス&免疫力がガタ落ちしたのを痛感。医師もびっくりな高スパンでのトラブル多発に悩んでいたところに、yoiでの執筆の機会が。心身を立て直すべくフェムテック&インナーケアを導入し、現在の推しは、エクエルと婦宝当帰膠。来年の目標は、分子栄養療法と婦人科でのモナリザタッチ。

ライター
31歳 こども3歳(2021年・無痛分娩)/0歳(2024年・帝王切開)
1993年生。週刊誌記者、文芸編集者を経てフリーランスに。2児の母。
福井:出産後にこんなしんどさが待ってるなんて聞いてなかった! 産む前に知りたかった!......ということがありすぎたので、今回のテーマは「出産後の体のリアルを語ろう」です。
木土:確かに「聞いてないんですけど......」ってこと、めっちゃありました。教えておいてもらえたら多少は心の準備ができていたかも。
月島:妊娠から出産までのことは妊娠中に教わるけれど、出産後の情報ってあまりなかった気がします。
福井:産後は目の前の新しい生命を育てることに精いっぱいで、自分の体のことを話す機会ってなかなかないですよね。
無痛分娩でも、体へのダメージは不可避

木土:お二人は無痛分娩のご経験者ですよね。無痛分娩だと、本当に痛みを抑えて出産できるんですか?
月島:私は一人目が無痛分娩でしたが、痛くて悶えながら産みました......。予定日超過の破水スタートだったのですが、麻酔を打っても陣痛があったんです。どうやらお産の進みがかなり早いほうだったようで、麻酔を追加する段取りの最中に「もう子宮口開いてるから、分娩台でいきんでみましょう!」って、あれよあれよと。結局4時間近くいきんで、最後は汗だくでした。
福井:私の場合は予定日より1カ月以上早く破水してしまって、急遽入院することになったのですが、病院のベッドで安静にすること3日、一向に産まれてくる気配がないので誘発剤を使って陣痛を起こして、麻酔を打って、それでも苦戦して最後は吸引分娩でした。陣痛や胎動は感じたし、時間がかかったので「いつ終わるんだ......」と体力・気力的にきつかった。
木土:私は2回とも帝王切開でした。そういう意味では、帝王切開は「手術」なので、事前に聞いていた手順通りでした。でも、手術台の上に横たわっている間中、天井にあるオペ用ライトに自分のお腹を切るところが映るんじゃないかと、ずっとビクビクしてしまって。
月島:出産のスタイルにかかわらず、ゆったり穏やかな出産ってなかなかなさそうですよね。
福井:私は出産する前「無痛分娩=痛みゼロ」と思ってたけど、同じ無痛分娩でも人によってかなり状況が違うんですね。
出産後の体のしんどさと会陰問題

木土:帝王切開って確かに手術中は痛みがないですけど、出産直後は下半身麻酔が残っているから自分で立つ・座るができないんです。お腹に力が入らないと、水を飲みたくても起き上がれないし、腕も伸ばせない、声も出ないことを知って愕然としました。電動ベッドの操作ボタンが命綱で「雪山で遭難して助けを待つってこういうかんじかも......」と思いました。
月島:私がいちばんつらかったのは会陰切開の傷。縫われた部分がつっぱって、歩いても座っても痛くて。産後2カ月くらいまでは円座クッションに相当助けられました。
福井:私は切開の傷はそこまでじゃなかったかも? 人によると思いますが、会陰マッサージをしておいたのがよかったと言う方もいますよね。産んだ直後は全身が疲労感できしむような痛さがあったけど、1カ月検診の頃にはかなりマシになっていたかな。
月島:切られ方にもいろいろ種類があるんですよね。私は悪露(※産後に子宮から出る分泌液。子宮内の血液や羊水、胎盤などが混ざったもの)についても全然把握していなくて「産み終わってからもこんなに血が出るのって普通なの?」とびっくりしました。体が痛くて頻繁にトイレに行くのもつらいので、夜用ナプキンは多めに用意しておくべきでした。
福井:出産がつらさのピークと思いがちですけど、産んだあともいろんなしんどさが続きますよね。妊娠中は赤ちゃんのケアばかりを調べがちだから、自分の産後の体のことを想像する余裕がなかった。
母乳問題・むくみ問題

月島:産後1〜2日経つと、急におっぱいがコンクリートのように硬くなったのにも慌てました。触ったら熱いし、洋服が擦れるだけでもズキズキ痛かった。
木土:私はなかなか母乳が通らなくて、出産した病院とは違う、“痛いけど効果絶大”と有名なおっぱいマッサージ(桶谷式乳房管理法)を受診しました。マッサージ自体は痛みがなく、パン生地になった気分で15分ほどこねられていると、カチコチだったおっぱいがふわふわのマシュマロ状に変化して、母乳が噴水のように天井めがけて飛び散っていくという......! 院内で母乳の出をよくしてくれるハーブティーが試せたり、正しい授乳の仕方も教えてもらえたりしたので、とても参考になりました。
月島:とはいえ、いざ通ったら通ったで、今度は母乳パッドがないと服が濡れちゃうなど、新たな課題も出てくるんですよね。
木土:引っ張られた乳首がすり切れたり伸びたりするしね。熱が出る乳腺炎もつらかったな。実は、乳腺炎の症状に耐えかねたときも、桶谷式相談室に電話をしたら「すぐに来て!」と受け入れてもらえて助かったんです。万が一に備えて、最寄りの桶谷式相談室をリサーチしておくのもおすすめです。
福井:私は、おっぱいでは特に困ったことがなくて......。
月島・木土:えー!! それは羨ましい。
福井:でも、産んだ直後から驚くほどむくんだんです。産後はホルモンバランスの変化でむくみやすくなるらしいですけど、精神的にも不安定でたくさん泣いたりもしたからか、顔から脚まで、全身が水分で重くふくれました。
木土:わかります。退院する頃には自然に治りましたけど、脚なんて一時的にゾウみたいになりますよね。私は手の指まで太くなりました。
月島:私は、むくみって経験したことなくて......。
福井・木土:えー!! やっぱり人によって全然違いますね。
月島:抜け毛は困りませんでしたか? 私は産後2〜3カ月頃から大量に。ホルモンの影響とわかってはいてもギョッとするし、掃除が大変で。各部屋に掃除用のコロコロを常備しました。
木土:わかります。「うちのお風呂にハムスターいる?」って思うくらい毛玉がたまりますよね。
月島:産後8カ月を過ぎて、ようやく抜ける量が減ってきて一安心。髪が長いと赤ちゃんに引っ張られることもあるので、妊娠を機に髪をバッサリ短く切るのもアリだったかも。
福井:私も産む前から抜け毛がいつ来るのかと怯えてたんですが、実際はあまり変化がなかったです。妊娠中に頭皮マッサージをしてみたり、妊婦用の栄養サプリをこまめに飲んだりしたのがよかったのかなと思ってます。
出産後の体の変化は? セックスは? 子どもとの向き合い方は? シオリーヌの出産&育児体験記
授乳後のおっぱいは、梅干しみたいにシワが寄る!

—— 妊娠・出産を経て、生活環境はもちろんですが、体にも大きな変化があったと思います。その変化はどう受け止めていますか?
まず、自分の体から母乳が出る、という現象がかなりシュールで、今もまだ慣れない(笑)。おっぱいって授乳するたびに萎んで、梅干しみたいにシワが寄るんですよ! そこからまた次の授乳までにパンパンに張ってくる。そういう変化を、毎回のように不思議だな〜と思って見ていますね。
あとは、授乳によって痩せたことも大きな変化の一つです。YouTubeのコメントでも「スリムになりましたね!」と言われることが多いですが、かつて摂食障害に苦しんだ私としては、それがじんわり苦しくて。出産の前後で体型が大きく変化するのは当然のことなのに、母乳をやめて元の体型に戻ったら、「太りましたね」と言われてしまいそうで、少し怖くもあります。たとえ褒める気持ちであっても、私の外見についてはそっとしておいてほしい、というのが正直なところです。

—— 体の変化以外に、精神面では何か変化がありましたか?
出産したら自分の中から“母性なるもの”が湧いてきたりするのかな?と思ったりしましたが、特にそういうこともなく…。母になったからといって、気持ちは何も変わっていないと思います。「私とこの子がいて、人と人として関係性が始まった」という状況になっただけ。ただ、保育園に行きはじめて多くの人と関わるようになったり、「この子の母親」として出会う人が増えると、そう思えないこともあるかもしれない、とは覚悟していますね。
確実に変わったことも一つあります。それは、「防災への意識」。避難グッズも見直したし、「地震が起こったらどうしよう」「前から来た車がぶつかってきたら…」と考えることが増えました。自分でも意外でしたが、出産したら危機管理能力は確実に高まった気がするな。
寝る間もない子育て中は、「セックスなんて無理」が本音かも

—— この連載のVol.9では「子育て中のセックス、みんなどうしてる?」というトピックで、実際に妊娠・出産を経験された方々と話し合いましたよね。インスタグラムで募集した、産後の性への意識アンケートでも、「膣=産道という認識になってしまった」「世の中にあふれる性的なコンテンツに嫌悪感を抱くようになった」という声がありました。シオリーヌさん自身は、何か変化を感じることはありましたか。
私は、産前・産後を通して、性に関して特に大きな変化は感じていません。医学的には、産後1カ月の健診で問題なく体が回復していれば、性交はOKになります。実際に、ひと月ちょっとで自分の体も本調子に戻ってきていたので、「しようと思えばできるんだろうな」という感じではありました。ただ、欲求的な部分はというと、疲れていたり眠いときって、それどころじゃないですよね。今はあまりにも子育てが忙しくて疲れているので、セックスよりも寝る時間を優先したいというのが正直なところ。でも、夫であるつくしとのスキンシップに嫌悪感を抱くようなことはないです。
—— 嫌悪感を抱いてしまう場合と、そうでない場合、その違いはどこにあるのでしょうか…。
ホルモンバランスの関係はもちろん、「どこまで子育てを一緒にしているか」も一つの理由として挙げられると思います。自分は子育てを必死に頑張って疲れているのに、向こうは育児も参加せず、今までと同じようにスキンシップを求めてきたら…そう考えると、嫌悪感がつのって愛情がなくなってしまのはよく理解できる。だから家族の関係を良好に保つためにも、パートナーと一緒に育児を担っていくことが大切だと、個人的には思いますね。

生き方もジェンダーも、いずれこの子が決めること

—— 産まれた赤ちゃんの性別について、YouTube動画では「将来的にこの子がどうしたいか、どう生きていきたいかはわからないけれど、現状では女の子ということになっています」というふうに紹介していましたね。
以前のインタビューでも話しましたが、私たちは妊娠中から、赤ちゃんの性別は公表しないようにしていたんです。「男の子だからこう」「女の子だからこう」といった固定観念を、生まれる前から押し付けたくないなと思っていて。それは生まれてからも変わりません。子どもの服を買うときも、できるだけニュートラルなデザインのものを選ぶように意識しています。
でも先日、「もしこの子が大きくなって、すごくフェミニンなものを好む子に育ったとしたら、自分の小さい頃の写真を見返して、『もっと可愛らしい服が着たかった!』と思うかもしれないね」という話になって。それで最近は、なるべく幅広いジャンルの服を買うようにしているんです。あらゆるジャンルを網羅しておけば、大きくなったときに本人が「これいいね!」と思える服を着た写真が1枚くらいはあるかもしれない(笑)。だから、あえてフリフリの可愛らしい服も買っておこうと思っています。早く自分の意思で好きなものを選べるくらい成長してほしい! 本人が望むなら、上がドットで下がボーダーでも、なんでもいいんです。
—— シオリーヌさんのお話を聞いていると、赤ちゃんをひとりの個人として、リスペクトする意識が感じられます。
視聴者さんからも、「オムツ替えのときの声かけが、対赤ちゃんではなく、対人という感じがする」とコメントいただきます(笑)。助産師をしていたときも、新生児に赤ちゃん言葉ではなく、丁寧語で話しかける癖があって。ただ、これから子どもが成長していく中で、一緒に過ごす時間が長くなればなるほど、冷静でいることが難しくなってくるのかもしれません。この子をコントロールしようとしてしまったり、選択肢を狭めてしまうことが出てくるかもしれない。もしそういうことがあったら、つくしとお互いに指摘し合おう、と言っています。
子どもがいても、自分の人生を充実させる意味

—— お話を聞いて、すごくシオリーヌさんらしい子育てだと感じました。
まだ出産して間もないですが、最近子育て支援事業を行う会社を設立したり、「いつか大学院に行きたい」という目標があります。ただ、そうやって挑戦したい気持ちが湧くたびに、心のどこかで「子どもがいるのに、いいのかな」と後ろめたさを感じてしまうこともある。これは、きっと多くの親が向き合っている葛藤で、今後もずっと悩み、考え続けていくことかなと覚悟しています。
ただ、この子が大きくなったとき、「本当は起業したかったのに、子育て中だったから我慢した」とは、絶対に言いたくない。子どもにとって居心地のいい親であるためにも、私は自分の人生を充実させなければいけない、と思っている。だから、子育てをしながらでも、自分の人生でやりたいことは、今後も挑戦していくつもりです!
うっかりミスに集中力の低下…これってもしかして「マミーブレイン」? 出産後の変化に落ち込むKさんのストーリー
産後10カ月で仕事復帰するもミスの連続

ベンチャー企業の営業として忙しい日々を送るKさん。産後10カ月でフルタイム復帰したものの、ペースを取り戻す以前にミスが続いてすっかり気持ちが落ち込んでしまったのだそう。
「大事なメールの送信や取引先とのアポイントを忘れてしまったり、夫と分担している子どものお迎えの日を勘違いして保育園に行ってしまったり。もともと几帳面な自分にとっては考えられないようなミスが続きました。しかも、まわりの人から指摘されて気づくことが多くて…。頑張ろうと思っているのに、信じられないミスをしてしまう自分がどんどん嫌になっていきました」
大きな不安を抱えながら、思い当たる症状を検索した末にたどり着いたのが「マミーブレイン」という言葉。医学用語ではありませんが、出産後に記憶力や集中力、思考力や判断力の低下がみられる状態を意味する言葉として、一般的に使われています。
「カレンダーに大きな文字で予定を書き込んだり、ささいなことでもメモを取ったりと、自分なりに工夫してきました。でも、ミスをしてしまうのが怖くて同じことを何度も確認するので仕事のペースも遅くなり、なんだか自分のスペックが落ちたような気がしてかなりネガティブになっています。また、子どもが2歳になったつい最近まで、症状が長く続いていたことも気になって…」
そこで、Kさんが感じている症状や不安を精神科医の岡田夕子先生に相談してみることに。
Kさんが気になっていること
1. マミーブレインは私の努力不足が原因?
2. 出産前の自分に戻れるかどうか知りたい。
3. 出産後のリスクを考えると、正直、第2子はあきらめるべき…?
精神科医
医師×YouTuber×Webライターとして、さまざまな分野で才能を発揮。YouTubeチャンネル『精神科医・みずきのこころチャンネル』では、こころの病気や症状、悩み解決方法などについて、自身の体験談なども交えながら発信している。
さまざまなダメージの蓄積が引き金に

Kさん 先生、マミーブレインが起こるのは私の努力が足りないせいですか? それとも、ホルモンなどの影響が大きいのでしょうか?
岡田先生 産後に忘れっぽくなったり集中力が低下したりするのは、Kさんのせいではありません。マミーブレインの原因はまだ明らかになっていませんが、精神的にも身体的にもさまざまな負担が加わることが要因と考えられています。
①睡眠不足
出産によるダメージを癒す暇もなく育児が始まり、睡眠不足に陥る人がほとんど。睡眠不足は集中力や注意力の低下を招く。
②疲労
出産してしばらくは十分な睡眠時間を確保するのが難しいのはもちろん、ゆっくり休むこともできないため疲労がたまってしまう。
③ホルモンの影響
妊娠中に多く分泌されていたエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)は、出産後にも大きな変化を遂げるといわれる。
④脳の萎縮
出産後は脳が4~8%ほど萎縮するという研究結果も。集中力や記憶力への影響はまだ明らかになっていないが、もしかすると関係している可能性も考えられる。萎縮は通常、6カ月ほどで元に戻るといわれる。
人によって違いますが、例えば実家が遠いなどの理由から夫婦だけで育児を頑張っている、ストレスを抱えやすい環境があるなど、①や②の要因が大きいと症状が現れやすい傾向があるのではないかと思います。また、根本的な治療法がないので、生活で自分なりに工夫していくことが必要になります。
Kさん 確かに、完全母乳だったことやワンオペ育児となる日も多く、毎日寝不足で…。子どもが2歳になった頃から、ようやく一晩続けて眠れるようになりました。
岡田先生 それは大変でしたね。寝不足は脳の回復を遅らせるので、できるだけ眠る時間を確保する方法を探してみましょう。例えば、昼間に搾乳して冷凍しておけば夜は解凍するだけなので、完全母乳でもパートナーと交代して眠れるようになります。仕事では、Kさんが実践されているようにメモや付箋、リマインダーを活用したり、場合によってはチームでスケジュールを共有したりするのも手だと思います。
Kさん この状態はずっと続くのでしょうか?
岡田先生 症状には個人差がありますし、生活環境やお子さんの特性などによっても違いますが、マミーブレインは出産に伴う一時的な症状です。ほとんどの人が1〜2年で回復するので安心してください。ただ、心や体に違和感を感じたときは、ささいなことでもかまわないので病院に相談してほしいと思います。Kさんは誰かに相談されましたか?
Kさん まさか。自分だけの悩みだと思っていたので、病院にも行政にも相談しませんでした。
心と体の違和感に気づいたら迷わず相談

岡田先生 そうだったんですね。実は、マミーブレインの症状の多くが、うつ状態のときに現れる症状と共通しています。産後うつは放っておくと悪化してしまうので、自己判断で「マミーブレインだ」と決めつけてしまうと、実際にはうつ症状だった場合の対応が遅れてしまいます。そうならないためにも、ささいな不調でも医師に相談することをおすすめします。相談してマミーブレインだとわかれば、それはそれで安心ですから。
Kさん そういう場合は精神科を受診するのでしょうか。
岡田先生 まずは、いつも通っている産婦人科や婦人科でかまいません。知っている先生のほうが相談しやすいでしょうし、必要があれば専門家につないでくれるはずです。
Kさん 違和感といっても自分では気づきにくいかも…。例えばどんなことがありますか?
岡田先生 あくまで一例ですが、次のような違和感を感じたら、かかりつけの医師に相談してみてください。
✔︎ 人の話を理解するのに時間がかかる
✔︎ 言葉がとっさに出なくなる
✔︎ 物事が覚えられない
✔︎ 読解力が低下する
✔︎ 何をしようとしていたのか忘れる
✔︎ 頻繁に物をなくす
✔︎ 忘れ物が増える
✔︎ 複数の仕事を同時に行なえない
✔︎ 仕事でミスが増える
✔︎ 疲れているのに眠れない/目が覚めてしまう
✔︎ 食欲がない/少量で満腹感を感じるようになった
✔︎ ついネガティブに考えてしまう
✔︎ 何かをする意欲がわかない
✔︎ あまり人に会いたくない
✔︎ イライラする
✔︎ 自分のケアはあと回しになっている
✔︎ 理由もないのに不安になったり、悲しくなることがある
✔︎ 子どもをかわいいと思えないことがある
先ほど、Kさんは「私の努力が足りないせいですか?」とおっしゃいましたが、日本社会においては、何か不調やトラブルが起きても「自分がもっと頑張ればいい」と自らを責める人が多かったり、「人に迷惑をかけてはいけない」と自己責任として抱え込んでしまう傾向があります。でも、頑張りすぎて心や体が壊れてしまったら本末転倒。助けを求めることが、結果的に自分もまわりも守ることにつながるんですよ。
Kさん こういうことってすごく個人的な悩みだと思っていたけれど、お医者さんに相談してもいいんですね。
岡田先生 もちろんです。相談するかどうかを迷ったり心配する必要はありません。「マミーブレインかも」「疲れているだけだから」と自分で症状に名前をつけず、自分に起きていること、感じていることを医師に伝えてください。そこに蓋をしてしまうと、体調やパートナーとの関係性にもひずみが出る可能性があります。
Kさん そういえば、寝不足や仕事復帰で疲れているせいか、夫と話すとイライラします…。
岡田先生 多くの人は「自分は大丈夫」という思い込みから、違和感に目をつぶって心や体からのサインを見逃しがちです。ですが、歴史的にみても出産は多くの女性が命を落とす原因のひとつ。まさに命懸けの行為ですから、マタニティブルーズ、産後うつ、マミーブレインといった変化は、誰にでも当たり前に起こるかもしれない。そう考えるほうが自然だと思いませんか。
お互いに歩み寄りながら選択肢を増やす

Kさん 最近は少し落ち着いているのですが、気持ち的にネガティブなスパイラルに入っていたのは事実です。仕事はもちろん、子育てでもパフォーマンスを発揮しないと母として評価されないのではとフラストレーションがたまってしまって。だからこのままじゃ第2子はリスクが高すぎると思うし、正直あきらめるべきかなと思っています。
岡田先生 お話を伺っていると、Kさんはとても頑張り屋さんですよね。ご自身も感じていらっしゃるとおり、今は二人目を考える前に、まずKさんが元気になることが何より大切です。本来は、子どもを育てることも、お母さんを守ることも、社会の役割。先ほどお話しした医師はもちろん、家族や友人、行政の制度など、少しずつでも周囲を頼ってみてください。そうすることで選択肢を増やせますから。
Kさん 夫は授乳以外の家事を分担してくれているので、完全母乳にしているぶん寝かしつけぐらいは私がやらなくちゃと思っていたし、実家やベビーシッターなど人の手を借りることに難色を示す夫の意向もあって、「誰かに頼る」という選択肢はなかった気がします。
岡田先生 Kさんもパートナーも、自分の親が家事育児を完璧にこなしているように見えたことで、「自分たちもそうあるべき」と考えているのかもしれません。ただ、現実は思い通りにはいきませんよね。実家やファミリーサポートなどのサービスも含めて、いろいろな選択肢に頼っていいんです。どんな選択肢を選んでいくか、ご夫婦で話し合ってみてはどうでしょう。
Kさん 最近は夫へのイライラが強くて、話し合うのは難しいかもしれません。
岡田先生 それはやはり、体調が万全ではないことが大きいかもしれませんね。それに夫婦といっても、別々の環境で育ってきたのだから意見がずれるのは当たり前。大切なのは、「完璧」にこだわることでも、片方が“折れる”ことでもなく、お互いに譲り合いながら二人なりの家族像をつくっていくことだと思います。
自分が元気になるための時間をつくる

Kさん 今は疲れているだけだとしたら、睡眠時間が増えれば元気になれますよね?
岡田先生 確かに疲労は睡眠でかなりリカバリーできますが、もし疲れているのに眠れないようなら医師に相談してみてくださいね。実は、眠れない、食べられないというのは、気持ちが落ち込んでいるサインであることが多いんです。女性は一生のうちにおよそ10人に1人がうつを発症するといわれていて、産後は特になりやすい時期なので、放っておいていいことはありません。
Kさん ほかにできることはありますか?
岡田先生 一人の時間をつくることも効果的だといわれています。どうしても子ども優先になりがちですが、お子さんが大きくなるまでにはまだ時間がかかります。ですから、子どものためにも、パートナーと対等に話し合うためにも、Kさんが心身ともに元気でいることが何より大切です。
Kさん 言われてみると、一人の時間はほとんどないかもしれません。
岡田先生 ご自身の回復のためにも、パートナーと協力してぜひ時間をつくってください。家で好きなことをしたり、ランチや美容院へ出かけたりする時間を持つことで心も回復していきますよ。
Kさん でも、一人で好きに過ごすってなんだか後ろめたくて。
岡田先生 そこは割り切ることも大切です。とはいえ罪悪感を持ってしまうと続かないので、“回復のための時間”とKさんご自身が割り切れる頻度を考えてみましょう。週1回は無理でも、月1回なら…など、自分が納得できるペースでかまいません。そして、マミーブレインに限らず、妊娠・出産によって起こる変化を欠陥だと思う必要はありません。親が健康でいることは、子どもの健康のためにもとっても大切。自分を責めるのではなく、できることを考えていきましょう。
ガルガル期、上の子可愛くない症候群、産後うつ病…経験者が語るメンタル変調のリアル 「Stories of A to Z」Story14

母性看護専門看護師、助産師、看護学博士
ウィメンズヘルス・アドバイザー、キャリアサポート・アドバイザー。NPO法人フィットフォーマザージャパン理事。西武文理大学看護学部准教授。母性看護専門看護師として女性の困りごとに耳を傾けつづけ、女性の一生をサポートしている。
「上の子可愛くない症候群」かも…と自己嫌悪に陥ったLさん
「上の子可愛くない症候群」かも…と自己嫌悪に陥ったLさん
「実は断続的に『上の子可愛くない症候群』でした」と、当時を振り返るLさんは2児の母。1年半ほど前に第2子を出産し、ほぼワンオペでの育児を続けてきました。気持ちの変化を感じたのは、当時長男が3歳、次男が生後2カ月を迎えた頃。
「今思えば、⻑男も赤ちゃん返りしていたのだと思いますが、着替えや靴の脱ぎはきといった普段なら一人でできることを『ママにやってほしい』と言ってくるようになったんです。私は次男の世話で手を離せないことのほうが多く、長男が自分でやってくれないことに必要以上にイライラするように。ものすごく些細なことでも、怒り出すとどんどんヒートアップする自分を止められなくて…子どもが寝たあとに反省しながら自己嫌悪に陥っていました」
長男のそうした言動は、その後4カ月ほどで落ち着いたそう。Lさん自身も、次男が1 歳を過ぎ、親の手と目が離せるタイミングが増えるにつれて、コントロールできないいらだちはおさまっていったといいます。
「次男はお兄ちゃんが大好きで、今は二人が仲良く遊んでいる姿が微笑ましいです。私の『上の子可愛くない症候群』は、産後うつ病の一種なのかもしれない。あのとき、どう対処すればよかったのかな…と今もふと考えます」
一人育児と二人育児はまったく別物。ゼロからのスタートだと考えて!

長坂さん 3歳児と0歳児をほぼワンオペで育ててこられたLさんは、本当にすごいと思います。まわりからは、「次男が生まれたときにはもうママ歴3年」と見られるかもしれないけれど、「2児のママ」としては0カ月のスタートなので、初めての経験だらけですよね。それから、医学的に「上の子可愛くない症候群」という診断名はないんです。しかもこれは、そもそもネーミングがよくないと思います。Lさん、「移行」って聞いたことはありますか?
Lさん いいえ、初めて聞きました。移行って何ですか?
長坂さん 移行というのは、「慣れ親しんだこれまでの世界を離れ、未知なる新たな世界に飛び込むことで、比較的安定した状況から新しい安定した状況への通過点であり、それは未知と不確実さのあいだにいる」(※1)と説明されています。ちょっと小難しそうに聞こえるけれど、実は人生の節目で誰もが経験していることなんですよね。例えば、学生から社会人になるとき、結婚して妻/夫になるとき、親になるとき、そしてLさんがご経験されたように、「〇〇くんの親」から、「二人のお子さんの親」になるときなどです。
「二人のお子さんの親」として新たな役割を身につけ、多くの変化が生まれる時期ですから、精神的な余裕がなくなって怒りっぽくなったり不安になったり、体のマイナートラブルが起きたりするのは当然の反応なんです。だからこそ、この時期は特に周囲のサポートが必要!
Lさん そうだったんですね…少し安心しました。
長坂さん Lさんは、上のお子さんが寝たあとに反省されていましたよね。「子どもが寝たあとに反省する」という経験は私にもありますし、多くのママから聞かせてもらう相談でもあります。「反省」を吐露されるママたちのお話をゆっくり伺うと、「赤ちゃんが泣くと、上の子を我慢させてしまったり、あたってしまったりするんですよね」といったように、実は、お子さんに対する気持ちというよりも、慣れない2児の子育てやワンオペの状況、育児に関係のないストレスなどに悩まれていることも多いんです(※2)。
これはサポート不足も関係していることが多いので、ご自身を責める必要はないし、責めてもうまくいきません。Lさんが本心では上のお子さんとどうかかわりたいと思っていらっしゃるのか、そのためにどんなサポートがあったらいいのかということを、ご家族やまわりの方と話し合えるといいですね。
※1 出典:Golan N (1981) Passing through transitions: a guide for practitioners. The Free Press, New York.
※2 日常的に「怒りがこみ上げる」「この子がいなかったら」などと感じる場合は、専門職に相談されることをお勧めします。乳幼児健診や保健センターでの育児相談の機会も利用でき、そこには、小児科医師や看護職などの専門職スタッフがいます。
二人同時に愛することはできる。ただ、手が足りないだけ

Lさん 長男とどうかかわりたいか…考える暇もなかった気がします。
長坂さん 例えば、上の子にイライラしてしまう状態の根っこにある本心は、「上のお子さんと離れたい」のか? それとも逆に、「赤ちゃんがいないところで上のお子さんとゆっくり過ごしたい」のか? 実は「ワンオペの状況に腹が立っている」のか? 相談の場でも、「どうしても下の子につきっきりになるけれど、本当は上の子ともっと触れ合いたい」とおっしゃる方が多いんです。もしかしたらLさんも、以前のように上のお子さんとゆっくりかかわる時間が取れないことへのストレスや、焦りを感じたりしていませんでしたか?
Lさん 言われてみると、思うように長男の相手ができないことへの罪悪感やいらだちが、イライラにつながってしまっていたかもしれません。
長坂さん 世話にかける時間=愛している証しではないと思うんです。二人のお子さんを同時にいつくしんでいるけれど、腕は2本しかないから一人しか抱っこできない。現実的に手が足りないだけなのに、「子どもたちそれぞれに対して、自分はうまくできない」と悩まれる方も多いんです。物理的な限界と、ご自身の愛情を混同してしまうと、自分を責めることにつながってしまうので、できるだけ切り離して考えることが大切だと思います。それから、Lさんは「産後疲労」も感じていたのではありませんか?
Lさん もちろん体は疲れていましたが、それは育児をしているみんな同じですよね?
長坂さん 産後疲労は、体の疲れだけでなく、睡眠不足や育児困難感、サポートを頼める人がいないこと、などが総合的に含まれます。産後疲労がたまると、「余裕のなさ」や「いらだち」を感じるというデータもあります。「イライラしてしまうな」「余裕がなくなっているな」と感じたら、数時間でもいいので頑張っている体と心を休めてあげることが大切です。といっても、周囲のサポートがなければ休む時間をつくれないのも現実ですよね。だからこそ、一人目、二人目にかかわらず、①産後はサポートを要請すること ②外部支援サービスの調整も含めて、まわりの方はママが休めるように家事や育児を担当することを、ぜひ心がけてほしいと思います。
Lさん あの頃、世話にかける時間と愛は違うんだと知っていたら、もっと楽になれた気がします。まわりにサポートを求めることも含めて、身近な人たちに話してみようと思います。
産後うつ病の治療をしたいけれど、ワンオペ育児で治療をためらうMさん

3年前に出産し、家族3人で暮らすMさん。子どもが生後4カ月を迎えた頃に産後うつ病を発症しました。
「娘がほとんど寝ない子で、下におろそうとすると泣いてしまうので1日じゅう抱っこ。家のことも自分のこともほとんどできない状況が続いていたある日のことでした。いつものようにベビーカーでお散歩中に信号待ちをしていたら、近づいてくる大型のトラックを見て“あ、あのトラックに突っ込みたい”と思ってしまったんです。その瞬間に娘が泣いたので、ハッと我に返って思いとどまったけれど、そのあとはもう歩くこともままならなくて。どうにか夫に電話をして、仕事を早退してきてもらいました」
パートナーは育休が取れず、里帰りできたのは5日ほど。そこからはずっと一人での子育てが続いていたといいます。
「もともと、パニック障害で心療内科に通院していたので主治医に相談したけれど、薬の種類もたくさんあるので自分に合うものを探すのが大変で…。合わなければ副反応が強く出てつらいし、合う薬が見つかっても服用するとぼんやりしてしまったり、やる気が削がれてずっと横になっていたくなったり。手のかかる子をワンオペで育てている私は薬を飲むことができず、治りも遅い状態です」
主治医、パートナー、家族…みんなでサポート体制を整える

Mさん 私のような状況でも、育児と並行できるうつ病の治療法はないのでしょうか?
長坂さん パニック障害の治療をされていたMさんのように既往症がある方は、安心して育児ができるよう、妊娠中から産婦人科医・精神科医、助産師を交えて、ご家族と産後に向けた調整をしてサポート体制を整えていきます。例えば、パートナーに育休や時短勤務、在宅ワークなどの体制を整えてもらったり、ご実家からの支援状況を確認したり、お住まいの自治体で利用できる妊娠中や産後のサービスを調べて申し込んだり。ご本人の希望や了解を得て、担当の保健師さんとあらかじめつながっておく場合もあります。治療のために薬が飲める環境、夜眠れる環境をつくることが大事なんです。ところがMさんは、頑張って、頑張って、ワンオペ育児をされていたんですよね…それは本当に大変だったでしょう。大きな負担を感じられていたのではありませんか。
Mさん とても寝ていられる状況ではないですね…。それに抗うつ薬はクセになりやすいとも聞くので、そういう不安もあります。
長坂さん Mさんは、①うつの薬の依存性 ②薬を飲むとぼんやりして育児ができなくなることのふたつを気にかけておられたのですね。ご自分が気になっていることは、気を遣うことなく、ご家族や主治医に伝えていいのです。むしろ、伝えたほうがうまくいきます。薬の飲み方はとても大事なので、主治医に細かく相談したほうが、ご自分に合った対策が立てやすくなりますよ。
Mさん そうなんですね。
長坂さん 産後の生活については、妊娠中から産婦人科や助産師外来でも相談できますし、産後は自治体からの新生児訪問や、保健師さんとの面談で相談すると自治体の産後ケアにつなげてもらえることもありますよ。ぜひ相談してみてくださいね。
子どもは社会で育てるもの。一人で抱え込まないで

Mさん 一応、現在も心療内科には通っているのですが、子どもを連れて行けないので親に預けて月に1回通うのがやっとの状態。「預かり保育を使えば?」とも言われるけれど、もしそこで子どもが病気をもらってきたら…などと悪いほうに考えてしまって、利用をためらっています。自分にできるケア方法ってありますか?
長坂さん まず、Mさんには通院したいという意思がおありですよね。ここが大切なポイントだなと思いました。その意思をパートナーやご家族に率直に伝えて、お子さんを見ていてもらうか、預けられるように調整してもらうのもひとつの方法です。例えばパートナーが月に1回でも仕事を調整すれば、現状+1回で月に2回は通院できるかもしれませんね。
Mさん 夫に仕事を調整してもらうのは申し訳ない気がして…。
長坂さん “トラックに突っ込みたい”と思ってしまった日、Mさんはパートナーに電話でSOSを発信できましたよね。それは、Mさんが持っている大きな力です。電話を受けて急いで帰ってきてくれたパートナーも、状況を判断したうえで仕事を調整できる強みをお持ちだなと思いますが、いかがでしょうか。お二人の関係性を考えても、Mさんが相談すれば、一緒に考えてくれそうな気がします。どうしても難しい場合は、数は少ないけれど、心療内科でもオンライン診療に対応しているクリニックもあります。
Mさん オンライン診療なら受けられそう。でもまずは改めて夫にも話してみます。
長坂さん 先ほど、自分にできるケア方法を知りたいとおっしゃっていましたが、Mさんは何事も「自分でやらなきゃいけない」と考えることが多いのではありませんか? メンタルの不調を抱えながらのワンオペ育児に加えて、Mさんだけがセルフケアを頑張ることは得策ではありません。子育てには、複数のサポーターが必要です。少しずつでもいいので、誰かと一緒に子育てをしながら「一人じゃない」「完璧じゃなくてもいい」という経験が積み重なっていくといいですね。
Mさん 自分でやるのが当たり前だと思っていたので、すぐに変えるのは難しいかも…。でも、まずは自分の思いを口にすることから始めてみようと思います。
身近な人の言動が気になってイライラが止まらなかったNさん

7歳と3歳の子どもを持つNさん。第1子を出産したあと、パートナーや家族へのイライラが募り、落ち着かない日々を過ごしていたといいます。
「夫が家事をしていても、何をするにも雑さや乱暴さに気が立って、いちいち小言を言ってしまい、ギスギスした毎日でした。当時は母が手伝いに来てくれていたのですが、母がご飯をよそったあとにしゃもじを置いた場所が気に入らないというだけで『こっちに置いてって言ってるじゃん!!!』と私がキレてしまったことも…。今思えば、本当にどうでもいいことなんですけど(笑)」
パートナーや自分の親だけでなく、義理の母の言動にもたびたび心を乱されたのだそう。
「義母に子どもの世話をお願いしたとき、『孫を職場の人に見せに行く』と言い出し、さらに『自分じゃはずせないから』と、抱っこひもの背中のバックルをとめないまま出かけようとしたんです。また、別の日に家に来たとき、私の授乳枕を背もたれにしようとしたので、顔を引きつらせながら『やめてください』と注意したことも。本当にちょっとしたあやし方まで気になったのを覚えています…。産後のメンタルが不安定な時期に、身近な人との距離感を保つコツが知りたい!」
イライラのパターンを分析してみる

長坂さん これは多くの産後のママが経験される、気持ちや感情の波が大きくなる状態ですね。いわゆる「病気」ではありません。ホルモンのバランスが乱れることで、何に対してもイライラしやすい時期なんです。子どもの命を守ることに精一杯だからこそ、Nさんのように、赤ちゃんの安全や健康に関係することで身近な方とケンカになることもよくあります。
Nさん これっていわゆる、ガルガル期ですか? いろいろなことが気になって、うまく距離を取れずにいました。
長坂さん ガルガル期は、「産後のホルモンバランスの乱れにより、精神状態が不安定になる時期」を表すネットスラングですが、Nさんのご経験もそこに当てはまりそうですね。そして、うまく距離感を保つコツのひとつは、自分がどんなこと・どんなときにイライラしてしまうのかをリストアップしたり、信頼できる人を通じて相手に伝えてもらったりすることです。
たとえ身近な人でも、お互いに心地いい距離感を見つけるのは一筋縄ではいかないし、時間もかかることなので、この時期だけは物理的に会う場面を減らして距離を保つことで、うまくいっている方もいますよ。抱っこひもは安全性に関することですが、「安全」のとらえ方には世代間のギャップもあったりして難しいですよね。私も、義母とのあいだで同じようなことがありました。
Nさん 私だけじゃないんですね…。バックルをとめてほしいと伝えても「大丈夫よ〜」と言われて、ますますイライラして何も言えませんでした。
長坂さん そこでいろいろ言ったとしても、お互いに不快な思いをするだけで、相手が変わることは期待できそうにないですものね…。ところで、Nさんはご自分のイライラのパターン分析をされたことはありますか?
Nさん パターン分析ですか?
長坂さん はい。「家事」や「育児」、「安全・衛生」「コミュニケーション」、「疲労」や「月経サイクル」に「体調」、「朝の身支度時」や「夕方の食事どき」、「寝かしつけのとき」など、自分がどんな場面でイライラするのかを書き出してみると、パターンが見えてきます。例えば、あやし方は「育児」、しゃもじの置き場所は「家事」、抱っこひもは「安全・衛生」とグルーピングできますし、そこには「自分のルールを乱されたくない」などの理由があるはずです。
Nさん なるほど。それはわかりやすいかも。
長坂さん パターンがわかれば、パートナーと具体的にシェアできますし、まわりにサポートをお願いするときの振り分けもスムーズにできそうですよね。私たちは一人一人違うので、すれ違いは当たり前。だからこそ自分を知って、共有することで、うまくいくことも多いんです。
自分なりの切り替えTIPSを見つけておく

Nさん それは子育てに限らず、いろいろなことに応用できそうですね。とはいえ、イラッとしてしまった瞬間に心を落ち着ける方法も知りたいです。長坂さんはどうしていたんですか?
長坂さん 私も苦労しましたよ〜。「イライラしたら5秒待つ」「飴やチョコレートを食べる」「外の景色を見たり、深呼吸する」など、怒りのコントロール方法としてよく挙げられることはひと通り試しました。あまりにイライラしたときは、子どもたちを夫に預けて“プチ家出”をして、自分のための時間をつくったことも2回ほどあります。
Nさん ちょっとした行動も、切り替えのきっかけになるんですね。パターン分析も含めて、少しずつ取り入れてみようと思います。
【産後ケア施設体験】働く母が活用するメリットとは? 費用や一日の過ごし方etc.出産後のライターがレポート!

注目度上昇中! 産後ケア施設とは?
出産後の母と赤ちゃんを対象に、心身のケアや育児のサポートを提供する「産後ケア施設」。授乳や沐浴のやり方を教えてくれたり、赤ちゃんを預かってもらって休息できたりするため、育児のスタートにもってこいのサービスです。
2021年より施行された「産後ケア事業ガイドライン」(厚労省)に基づいて、全国の自治体でケア施設の整備が始まりました。病院や助産院が対応しているほか、民間が運営する産後ケアホテルなども増えてきています。
私が2016年に長男、2019年に次男を出産した頃は、そんな施設は外国にしかないものだと思っていました。でも今年の9月に第三子を出産する前、いろいろと調べていたところ日本でもずいぶん一般的になっている様子。これは使ってみるしかない!と、計画分娩日の1週間ほど前に予約。働く母にどんなメリットがあるのか? 産後ケア施設の活用レビューをお届けします。
かかる費用や選ぶ基準のリアル
産後ケア施設にはデイサービス型、宿泊型、訪問型などがあり、自治体指定のケア施設を利用する場合は助成金が出ます。たとえば1泊2日の宿泊型ケアを使ったとき、利用者の自己負担額は渋谷区で7,000円、中野区で6,000円、品川区で7,500円。ビジネスホテルほどの料金で母子をサポートしてもらえるとあれば、なかなかリーズナブルです。でも、自治体指定の施設はあまり数がなく人気のため、すぐに予約が埋まってしまうことも……。
対して民間が運営する産後ケア施設は、基本的に助成金が適用されません。そのため、1泊2日の平均価格は4~6万円。ある程度まとまった日数の利用が必要なケースもあり、費用面のハードルが高いといえます。ただし、1日3食おやつ付きの豪華な食事やホテルライクな部屋が提供されたり、家族も一緒に泊まれたりするなど、サービスの充実はさすが。なかには、豪華ホテルの一室に泊まってインルームダイニングの朝食が楽しめる一泊約15万円~のサービスもありました。
いろいろ吟味したうえで私が選んだのは、民間の産後ケアホテル「Mamma Levata」です。1泊からでも利用できることと、家族の素泊まり無料が決め手になりました。飯田橋のホテルメトロポリタンエドモント内にあるため、都内からのアクセスも抜群。郊外型が多い産後ケア施設において、電車でも行きやすいのが助かりました。
いざ宿泊! 産後ケア施設での過ごし方をレビュー
【夕方~夜】お部屋にチェックイン

産後3週間のタイミングで、3泊4日利用することにした今回。初日は13時頃にチェックイン。赤ちゃんのおむつやミルクに着替え、ママのアメニティなどはひと通り用意されているので、荷物は必要最低限でOKです。
案内されたお部屋はツインベッドにソファー、テーブルがあり、思った以上に広々していました。ベビーベッドを入れてもゆったり過ごせる空間です。地味にうれしかったのが、個室内が土足厳禁のため自宅のように過ごせること。抱っこをするためにベッドから降りていちいち靴をはく……みたいなの、面倒ですもんね。

食事は毎回お部屋まで届けてくれるので、ぼーっとテレビなどを見ながらいただきます。ボリュームも十分で、母乳育児にも強い味方です。
22時すぎに授乳をしたら、赤ちゃんはベビールームへ預けます。ホテルの1フロアがまるごと産後ケア施設に充てられているので、ベビーベッドを運ぶときに人目などが気になることはありません。夜間はプロにお世話を任せて、ママがゆっくり休養できるのが産後ケア施設の醍醐味! ここぞとばかりにちょっとだけNetflixを観たけれど、23時半には眠りにつきました。
【朝】家事からの解放を実感!

思いっきり寝坊したい気もするけれど、胸が張ってきてしまうので、朝は7時に赤ちゃんを引き取って授乳です。そうこうしているうちに、お部屋に届く朝ごはん……!
産褥期に家事から解放されるの、本当に最高ですね。家にいれば上の子を学校に送り出し、下の子を起こしている頃でしょうか。ゆっくり朝ごはんを楽しんだあとは、無料オプションのよもぎ蒸しを使ってみました。

よもぎを蒸した蒸気でじんわりと下半身を温めて、子宮の戻りを手助けしてくれるのだとか。産後なのに、自分のために時間を使えるのが贅沢です。
【昼】友人の面会や美容室へ

お昼すぎには、仕事の合間を縫って友達が面会に来てくれました。アクセスのいい都心にあるからこそ、こんな時間も過ごせます。自宅じゃないので、人を招くために部屋を片付ける手間もありません。
そのあとは3時間ほど赤ちゃんをベビールームに預け、美容室へ! カットとカラーでさっぱりリフレッシュできました。産後こんなに早く美容室に行けるなんて思っていなかったなぁ……。ホテルに戻ったらちょうど授乳の時間が過ぎていたので、もう少し預けたままにして、いくつか仕事のメールまで片付けてしまいました。
赤ちゃんがいるとなかなか集中できないこと——例えば内祝いの手配やお宮参りの予約などを済ませたり、ちょっとした買い物に出かけたり。24時間対応の一時預かりサービスを使ってできることはたくさんありそうです。
【夜】家族とともにゆっくり就寝
今夜からは子どもたちも一緒に宿泊。2泊目は下の子と、3泊目は上の子と泊まり、兄弟とゆっくり過ごす時間も確保できました。家族の素泊まりが無料なのはとてもありがたいところ。ホテルの目の前にはコンビニもあるので、食事にも困りません。第一子なら、パートナーと一緒に泊まるのもよさそうです。
今夜も23時以降はベビールームにお願いして、ゆっくり就寝。頼んでおけば、預けているあいだに沐浴や体重計測などもしてくれます。育児の悩みをプロに相談して、アドバイスをもらうことも可能です。
【チェックアウト】心温まる心遣いも

最終日にはサプライズ! 赤ちゃんの写真と足形を取った、記念の色紙をプレゼントしてもらいました。たった数日しか滞在していないのに、温かく見守ってもらえてうれしかったです。産後のメンタルは不安定なので、細やかな心遣いが実に沁みます……!

働く女性が、産後ケア施設を利用するメリットは?
3人目の子どもとはいえ、5年ぶりの新生児育児で忘れていることばかり。そんなとき、ゆったり体を休めながらプロのサポートを受けられる環境は、とてもありがたかったです。
特に素晴らしいのは一時預かり。夜間も3時間ごとの授乳から解放されてゆっくり休めるので、産後3週間のまだ本調子ではない体が、いくらかラクになりました。抱っこや授乳で少しずつ張ってきていた肩や腰にも、この物理的な休息が本当にありがたいんですよね。家にいたら完全には逃れられない食事の準備や掃除、洗濯など、家事をしなくていいのも大きなポイントです。
そして何よりうれしかったのは、産後でも「自分」を後回しにしないで済むところでした。産後のママは「子どもが生まれたんだから」とつい気を張って、知らぬ間に自分を追いつめてしまいがち。でも、こうやって心身をケアできれば穏やかな気持ちでいられるし、また笑顔で赤ちゃんと向き合うことができます。私は産後すぐから仕事を再開しているため、ちょっとした集中タイムが取れるのも本当に助かりました。

民間の施設だとそれなりの費用はかかってしまうけれど、価値は確実にアリ。1~2泊でも十分にリフレッシュできます。産後のダメージが残る体で24時間お世話を続けるのは、どうしたって大変……! だからこそ一人で抱え込まず、ほんの少しでも赤ちゃんを預けて、ゆっくりする時間を取ることが大事です。休んでエネルギーを回復し、ちょっと時間を空けてふれあう赤ちゃんは、驚くほどかわいく思えます。里帰りやパートナーの協力が見込めない場合に、退院後すぐ産後ケアに入るママもいるそうです。
少しでも費用を抑えるには、自治体指定の施設を確保できるよう、早めの情報収集と予約が必須。産前から自治体の手続き方法をチェックしておきましょう。自治体、民間いずれにしても、産後ケアは産後3~4カ月までしか使えない施設が多いため、早めのご手配をお忘れなく。
便利なサービスをうまく活用して、子育てを楽しめるご家庭が増えますように。
Mamma Levata(ママ レヴァータ)

今回宿泊したお部屋は「マーガレット」
1泊2日 68,800円(素泊まり)/79,800円(4食付)
3泊4日 23万4,612円(3泊~6泊の利用で2%オフ)
https://mamma-levata.com/
今話題の「産後ドゥーラ」って何? 成り立ちからサポート内容、料金目安、家事代行との違いまで専門家が解説!

一般社団法人 ドゥーラ協会代表理事
松が丘助産院院長、助産師、(公社)東京都助産師会会長。区役所での勤務後、助産師の資格を取得、1998年に中野区に松が丘助産院を開業。2012年には『一般社団法人 ドゥーラ協会』を設立し、妊娠中から、出産・産後ケアまで、女性の包括的なサポートを行なっている。
「産後ドゥーラ」とは? どんなサポートをしてくれる?
●不安定になりやすい産前・産後の母親をサポート。ベビーシッターや家事代行との違いは?
「産後ドゥーラをひと言で表すなら、“母親に寄り添い、支えてくれる人”」と語るのは、『一般社団法人 ドゥーラ協会』代表理事の宗さん。
「もともと助産師として働くなかで、特に産後の女性が抱えるプレッシャーの大きさを感じていました。体もまだ回復していないのに24時間休みなく気を張って、そのうえ、家の仕事もしなければならない。誰かに助けを求めたいのに、身近に頼れる人がおらず簡単に声を上げることができない。当時はそんな人が本当に多かったんです。そこで、家事や育児はもちろん、母親のエモーショナルサポートをする人が必要だと思い、協会を設立しました。
ベビーシッターの場合は主に子どものお世話を、家事代行の場合は料理や掃除など、お願いした家事だけをサポートしてくれるのが一般的ですが、産後ドゥーラはタスクの垣根なく、包括的なサポートを柔軟に行なっています。例えば、『とにかく、今のつらい状況をどうにかしたい』という依頼が来れば、寄り添って話を聞いたり、『依頼した時点では子どもを見てほしかったけれど、当日になったら寝てしまったので、やはり料理をお願いしたい』というリクエストにも対応可能です。また、母親だけでなくほかの家族への沐浴指導なども行なっています」
会社からの派遣サービスではないところも、大きな特徴。資格を持った産後ドゥーラと利用者の間での個人契約として、サポートのプランを直接交渉できるので、各家庭のニーズに合ったきめ細かいサービスが提供できるのだそう。保育士や栄養士、整体やアロマセラピストの資格を持ったドゥーラを選択することもできます。

●料金体制は? 何歳まで利用できる?
「料金は、資格やサポート内容、地域によって変わりますが、1時間3000円前後が目安です。自治体によっては補助金が出る場合もあるので、(東京都では新宿区や中野区、江東区などの13区4市、その他神奈川県、千葉県、静岡県の一部地域など)一般社団法人ドゥーラ協会のHPや各自治体のHPなどから確認してみてください。
また、サポートは『産後』だけでなく、妊娠中から利用可能。子どもが生まれてから1年半までのサポートを想定していますが、“何歳以降は利用できない”という規定は設けていません。担当のドゥーラに、まずは相談してみてください」(代表理事・宗さん)
講義、実習、テスト、面談。養成講座で産後ドゥーラの高い質を保証
設立から10年がたち、ドゥーラ協会が認定する資格保有者は、約700人になるといいます。養成講座を受講し、試験、面談に合格すれば、「一般社団法人ドゥーラ協会認定産後ドゥーラ」の認定を受け、個人事業主として働くことができます。

●資格取得の方法
「協会では、妊娠・出産の知識に加え、産後のお母さんの心と体の状態を理解するための養成講座を行なっています。そのなかで、産後ドゥーラとしてのあり方、コミュニケーションの方法、乳児の保育実習、調理実習、救命救急実習など、産後のサポートに必要なあらゆる知識について学びます。高い質を守るためにも、この過程を私たちはとても大切にしています」(宗さん)
STEP1
産後ドゥーラ養成講座(講義・実習)
▼
STEP2
筆記試験
▼
STEP3
理事面談
▼
STEP4
修了式・産後ドゥーラ認定
▼
STEP5
開業研修
▼
STEP6
開業
▼
STEP7
フォローアップ研修
●資格取得までの期間は? 費用は?
受講から認定にかかる期間は、4カ月半程度。毎週1回、10時〜16時前後で授業があり、平日コースと、土日コースが選べる。費用は約40万円と決して安くはないものの、受講希望者は年々増加しているのだそう。
「子育て経験の有無は問いません。産後ドゥーラの活動に賛同する、25歳以上の心身ともに健康な女性なら誰でも講座に申し込むことができます。実際に幅広い年齢の方々がドゥーラとして活躍していますよ」(宗さん)
「産後ドゥーラ」として働く桑原恵美さんの仕事内容

では、実際に産後ドゥーラとして活動する方は、日々どのようなサポートを行い、母親たちとコミュニケーションをとっているのでしょうか。今回話を伺った桑原恵美さんは、ご自身も2児の母だと言います。
「産後ドゥーラとして働く前は一般企業に勤めていて、毎日朝から晩までバリバリ仕事をしていました。ところが、二人目の子どもを出産した際、次男が障がいを持って生まれてきて、家から一歩も出られない日があったりと、育児中心の生活に一変しました。あるとき病院の先生に、『あなたは、ご自身で思っているよりも大変な状況ですよ』と言われたことをきっかけに、ヘルパーさんをお願いすることに。とても助けていただきましたが、“ここまではできますが、ここからはできません”という制限もあり、また、私自身のエモーショナルサポートはもちろんなく、もっと包括的なサポートがあればいいのになと思ったのが正直なところでした。そんなことをオーストラリアに住む友人に話したら、『こっちでは、ドゥーラというサポートがあるよ』と教えてもらったんです。調べてみると、日本にも協会があることを知りました」(桑原さん)
産後ドゥーラについて知っていくなかで、サポートを受ける側を経験したからこそ、困っている人を助けることができるのではないか、と自身でも資格の取得を決意したそう。活動を始めて7年がたつ桑原さんが、サポートをする上で気を付けていることとは?
「まず、依頼者を絶対に否定しないことです。以前、あるヘルパーさんに『まずはお母さんが元気でいないと』と言われたことがあって、『こっちが元気になる方法を知りたいよ!』と、もやもやしたことを覚えています。産後は環境が大きく変わるうえにホルモンバランスも乱れ、自分が思っている以上にしんどい時期。そんな中で一生懸命育児をしているお母さんに、『あなたの選択、判断は間違っていない』と肯定する立場でいたいと思っています。
また、依頼者とほどよい距離を保つことも大切にしています。定期的にお会いしていろいろな話ができるようになったとしても、そこは必ず守ります。知り合いでもなく友人でもなく、他人だからこそ話せることがあると思うので。例えば何かを聞かれたら、自分が持っている情報は提示するけれど、その中からどれを選択するかは相手に委ねる。その選択を尊重しながら、ストレスを減らすお手伝いができたらと考えています」(桑原さん)
親も子どもも、個性があるから。教科書どおりにできなくて当たり前
出産、子育てに不安はつきもの。その不安を少しでも減らすために、気軽にドゥーラを活用してほしい、とドゥーラ協会創設者の宗さんは言います。
「産後の女性はとにかく頑張りすぎる傾向があります。『みんなやっているのに自分だけできない』『育児書に書いてある通りにならないのは、私のやり方が間違えているから?』など、誰にも相談できずに一人悩んでいる方はとても多い。でも、赤ちゃんもお母さんもそれぞれ個性がありますから、教科書どおりにならなくて当たり前。大変だと思ったら、気軽に産後ドゥーラに頼ってほしいです。ただ話を聞いてほしい、というご依頼でも構いません」(代表理事・宗さん)
サポートを利用したい場合は、ドゥーラ協会のHPから予約が可能。それぞれの得意分野や保有資格、対応可能エリアなどを見ながら、自分の要望に合ったドゥーラを探してみてください。
“産後ダイエット”以外の健康管理を考えたい! 体重管理をしない新しいパーソナルトレーニングの形
これまでは「ダイエット」でしか自分の体に向き合ってこなかった
——ご著書『食べるの怖いな』(ハガツサブックス)では、摂食障害のご経験をコミックエッセイにされていますよね。シオリーヌさんはこれまで、どのように自分の体に向き合ってきましたか。

食べるの怖いな/大貫詩織(ハガツサブックス)
シオリーヌさん:妊娠前は、「ダイエット」を通じてでしか、自分の体のことを考えてきませんでした。私が初めてダイエットをしたのは中学生のとき。体重が減ったことをきっかけにクラスの中心的存在のギャルたちにすごく褒められて、それが私のモーレツな成功体験になりました。大学生と社会人のときにも、「数カ月で十数kg痩せる」という急激なダイエットを実施。食べては吐き戻すを繰り返していました。
——最近、ニュージーランド在住のトレーナーmikikoさんから、健康指導を受けていらっしゃるそうですね。どのようなきっかけで指導を受けることになったのでしょうか?
シオリーヌさん:2023年の春に子どもが保育園に行くようになってから毎月子どもの風邪をもらうようになり、今も12月からずっと咳が止まらないんです。一緒に働いている方に迷惑をかけることも増えてきてしまって…必要に駆られて、健康管理について考えるようになりました。
また最近の健康診断で、出産前から10kg体重が増えていたことがわかり、今は本当に写真を撮られたりするのが嫌なんですよね。そういういろいろなきっかけが重なって、自分の体に関心が向いている状態です。
——「産後ダイエット」という言葉があるように、社会には「出産したら産前の体型に戻すべき」という考えが広まっているように感じます。
シオリーヌさん:実は出産後、YouTubeで産後ダイエットに関する案件の依頼がたくさん来ました。「痩せること」が仕事になるってとても怖いですし、自分の体型のことを他人からとやかく言われたくない。依頼が来ることで「今の私って産後太りだと思われているんだな…」と思い、落ち込みましたね。
そんなときにmikikoさんは、「出産前後では、子どもを抱っこするとか、外出時の荷物が違って、必要な筋肉量も変わっているから、今の生活に適応するために体が変化しているんですよ」とか、「出産後、2年近くかけて変わってきた体型を、数カ月で急激に変えるのは無理なこと。焦らず年単位で健康に戻していきましょう」と言ってくれたんですよね。産後の健康管理は、「急激なダイエット」だけじゃないんだなと思えるようになりました。
体重測定も、無理なトレーニングもない。新しいパーソナル健康管理の形
——取材時点で、パーソナルトレーニングを始めて3カ月とのことですが、mikikoさんとはどのようなことをしているのでしょうか?
シオリーヌさん:彼女はニュージーランド在住なので、基本的にはリモートで月に1回1時間程度時間を取って、トレーニングするのではなく、とにかく話をします。そこで最近の食事の内容や悩みを共有して、生活改善のためのアドバイスをもらうんです。
例えば、これまで私は、毎日の食事をウーバーイーツのジャンクフードで済ませていました。それを話したところ、「週5日ジャンクフードを食べていたのなら、まずは週3に減らしましょう。今までとギャップが大きいほどストレスが大きくなるので、むしろ週3はジャンクフードを食べてください」というアドバイスをもらい、ヘルシーな食事の回数を少しずつ増やしているところ。自分のための料理は苦手なので、ウーバーイーツの中でもヘルシーな鍋や魚のお弁当を一緒に探して、少しずつ改善しています。

バランスを考えて選んだお弁当と、カットフルーツ
——パーソナルトレーニングというと、厳密な食事管理や運動指導をされるイメージでしたが、食生活をベースとしたカウンセリングのようですね。
シオリーヌさん:私自身も、「パーソナルトレーニング=減量」「数カ月で短期的に痩せるもの」というイメージを持っていたのですが、そういうトレーナーさんばかりではないと思います。今は、「医学的に体重管理の必要があるような状況ではないのなら、体重は量らなくていい」と言われていて、mikikoさんに体重を伝えたことは一度もないです。焦らず食事や姿勢を少しづつ改善しながら、自分にとっていい状態を作れるように整えているところ。今の状況や気持ちを理解して寄り添ってくれるようなトレーニングが自分には合っていると思います。
自分のために、「アンチエイジング」ではなく「ウェルエイジング」を目指す

朝食前、子どもの食事を用意している間に飲むようになったプロテイン
——健康管理に向き合う中で、ハードルに感じていることはありますか?
シオリーヌさん:摂食障害だった過去の経験から、過激なダイエットの“頑張りスイッチ”が入りそうになるのを止めることです。「太っている自分が嫌い」という感覚が自分の中に根深くあって、頭の片隅で「健康管理のついでに痩せたらいいな」と思っちゃうんです。mikikoさんには、「大きな目標を決めたり、頑張ろうと思いすぎないでください」と言われていて、「私の仕事は、シオリーヌさんのモチベーションを折ることです(笑)」とさえ言われています。
健康管理を始めてからは、とにかく健康的に年を取りたいと思っているんです。「アンチエイジング」ではなく「ウェルエイジング」ですね。誰かに何かを言われたからとかではなく、あくまで自分のための健康づくり。その方法の一つとして、“痩せる”だけが目標ではない様々なパーソナルトレーニングが、多くの人の選択肢になればいいなって思います。
【優木まおみのフェムケアエクササイズ】PMSや出産後の悩みに。今日からできる骨盤底筋の鍛え方
身体美容家®︎・タレント・モデル
1980年3月2日生まれ、佐賀県出身。大学在学中に芸能界デビューし、グラビア、キャスター、レポーター、ファッションモデル、コメンテーターなど、マルチに活躍。第2子出産を機にピラティスインストラクターの資格を取得。ピラティスを元に発展させたオリジナルメソッド「マオビクス」を創始。オンラインボディサロンや全国のセミナー、レッスンで指導を行なっている。著書に『マオビクス 背骨から身体を変えるおうちピラティス』(リブレ)など。
正しい姿勢から、骨盤底筋やインナーマッスルを鍛えることが大切

優木さん「37歳での第2子出産後、不調に悩まされました。体が疲れ果て、心も落ち込むように。そんなときにピラティスに出合いました。ピラティスのメソッドには、体を芯——骨格の部分から整えるということがあります。そのためにまず行うのは、背骨をストレッチとマッサージでほぐすこと。だからハードな運動ができない状態でも始められて、そこから少し頑張ってトレーニングをしてみよう、と続けることができたのです」
——2019年にピラティスインストラクターの資格を取得し、気軽に取り入れられる背骨のストレッチをメインにした独自のメソッド「マオビクス」を確立した優木さん。現在は、自ら全国を回ってセミナーやレッスンを行なっています。
優木さん「PMSなど女性ならではのお悩みを抱える方々の体を見ると、普段の姿勢が良くないことが多いです。実は骨盤が正しい位置にないと、子宮を支える骨盤底筋をはじめとしたインナーマッスルが使えていない状態になります。まずは姿勢を自然に整えるセルフケアから、そして、骨盤底筋が機能して、鍛えられるトレーニングをご紹介したいと思います」

膣のゆるみにも効く! 骨盤底筋を自然に鍛える「正しい立ち方」
子宮、膀胱、膣、直腸など、女性にとって重要な臓器を支える「骨盤底筋」は、加齢によって衰えやすいもの。ここが使えていないと、膣のゆるみや尿漏れなどの原因にもつながっていきます。今回は日常的に意識することで骨盤底筋が自然と鍛えられる、正しい立ち方をレクチャーしていただきました。
骨盤底筋が鍛えられる正しい立ち姿勢とは?


立っている姿勢で両手で逆三角形をつくり、お腹の下のほうに当てます。人差し指の先が恥骨に、手首が腰骨にくるような位置に。この三角形の面が、地面に対して垂直になるようにして立つと、骨盤底筋が正しく働くと言われています。
骨盤がニュートラルな状態にある姿勢を保つためには、かかとの上に骨盤が来るイメージで立つと良いでしょう。体の重心は、足裏の長さのかかとから3分の1の位置に来ます。1枚目の写真が正しい姿勢です。
骨盤底筋が使えていないNG姿勢

背中が丸まり、恥骨が前に出るような姿勢を「骨盤後傾」と言います。骨盤が後ろに倒れるようなこの姿勢を続けていると、お尻が垂れてきたり、ハムストリングスが硬くなります。

恥骨が後ろに下がり、腰骨が前に出てくる、いわゆる「反り腰」。この姿勢が癖になると、肋骨が圧迫され、呼吸が浅くなります。腰を痛める方も多いです。
骨盤まわりを整え、インナーマッスルを鍛えるエクササイズ「ダイナソー」
普段の姿勢を正しく意識できるようになったら、インナーマッスルを効果的に鍛えるエクササイズにトライ。
優木さん「骨盤底筋は、横隔膜、多裂筋、腹横筋とカルテットのように働きあって、骨盤の位置を正しく保ちます。ご紹介する『ダイナソー』は、股関節を柔らかくするストレッチと、インナーマッスルの腸腰筋を使う強化トレーニングの2段階のエクササイズです。気軽に短時間で行えるので、ぜひ、日常の隙間時間に取り入れてみてください」
①股関節とインナーマッスルのストレッチ

【1】片足を前に出し、もう片方は足の甲を地面につけて後方に下げ、片膝立ちになります。
前の足は、かかとの垂直上に膝が位置する角度が目安です。体側に鋭角に曲がらないよう注意してください。立てた膝の上に軽く両手を乗せ、前を見て背筋を伸ばします。
【2】そのまま、腰を反りすぎないよう意識しながら、前方に力を加えてストレッチをしてゆきましょう。鼠蹊部が伸びるような感覚です。上体は、頭頂部が天井へと引っ張られるように、上にまっすぐ伸ばします。伸ばしながら何度か呼吸をします。
②腸腰筋の強化につながるエクササイズ

【3】呼吸を繰り返して、股関節がほぐれてきたら、後ろの足のつま先を立てます。つま先で地面を押すように、また、かかとを後ろに押し出すように力を加えましょう。
前の脚は足裏全体で地面を押し、体がぐらつかないように支えます。すると、後ろの脚の膝がぐっと伸びて地面から浮き、腰から上体が引き上げられます。
上半身はまっすぐに保ち、腰に負担がかからないように気をつけましょう。おへそを後方に下げて、恥骨を前に出すようなイメージで姿勢をキープ。足の付け根の筋肉が伸びていて、腸腰筋が体を支える形になります。
【4】数秒深呼吸をして、ちょっとしんどくなってきたな、というタイミングで膝をゆっくり下ろします。両側1回ずつでもいいので、ゆっくり呼吸をして繰り返してください。
優木さん「まずは普段から姿勢を意識するところから始めましょう。今すぐできるちょっとした習慣が、未来の自分を、ヘルシーに変えてくれるかもしれません」